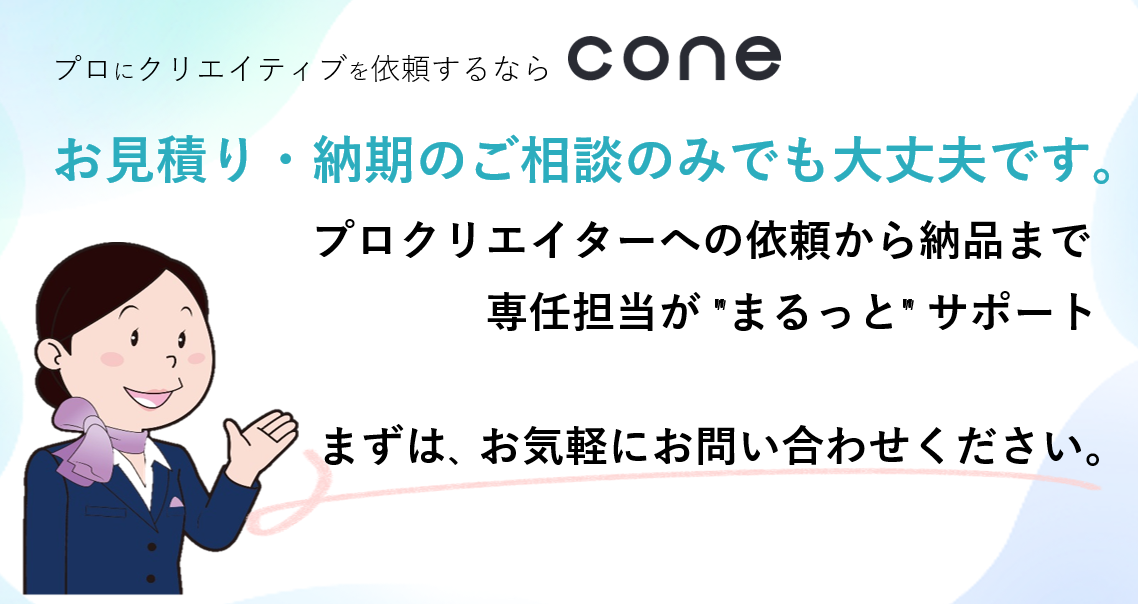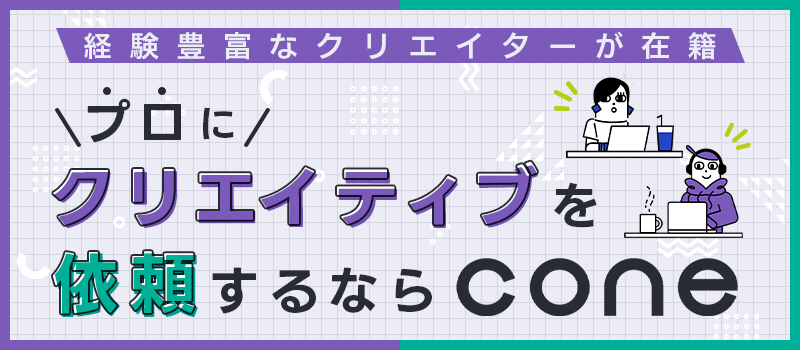小売業や飲食業などのサービス業の現場では、「接客スキルの標準化」や「新人教育の効率化」が大きな課題となっています。こうした課題解決策の一つとして注目されているのが、接客マニュアルの動画化です。
接客マニュアルを、紙ではなく動画で作成することで、文章や写真だけのマニュアルよりも、スタッフの表情や話し方、動作などが直感的にわかりやすく、効果的な教育につながります。
そこで、本記事では、接客のマニュアルを動画化するメリットと作成手順を解説し、動画化に適した業務とマニュアル作成・運用のコツを紹介します。
接客マニュアルを動画化するメリット
接客のマニュアルの動画化は、新人の育成を効率的に行いつつ、教育コストの削減、店舗や会社全体の接客クオリティの標準化ができるメリットがあります。
ここでは、それぞれのメリットについて解説します。
- 新人の育成
- 動画マニュアルは、実際の接客シーンを視覚・聴覚で再現できるため、接客の所作や表情、声のトーンといった「文章だけでは伝えにくい部分」が自然と身につきます。
例えば、お客様を迎える際の笑顔や声のかけ方、お辞儀のタイミング・角度などは、静止画では全体の流れや先輩スタッフの雰囲気まで伝えることは難しいでしょう。また、身だしなみの整え方なども映像で見せることで、理解が格段に深まります。 - 教育コストの削減
- 教育担当者が新人に対して個別に指導を行う必要がなくなり、動画を繰り返し視聴することで自己学習が可能となります。これにより、教育にかかる人件費や時間の削減が実現します。 特にアルバイトを多く雇用している店舗や人手不足の店舗、繁忙期など、教育に時間をかけられない状況でも即戦力の育成に活用できます。
- 接客クオリティの標準化
- 動画マニュアルを活用することで、教育担当者ごとの伝え方やニュアンスの違いが生じることを防ぎ、「店舗や会社が目指している接客」を誰に対しても均一に共有できます。
全店舗・全スタッフが同じ基準で接客を行うことで、ブランドイメージの統一にもつながります。
関連記事:動画マニュアルのメリットと作り方をわかりやすく解説
接客マニュアル動画の作成手順

サービス業の接客マニュアルの作成は、以下のように作成の流れを順序立てて行う必要があります。
- 1.接客プロセスの洗い出し
- まず、接客に関わるすべての業務内容をリストアップします。 来店対応から会計までの一連の業務、クレーム対応、清掃作業まで、店舗で実際に行われている業務をピックアップすることで、マニュアル化すべき内容が明確になります。
- 2.接客ルールの洗い出し
- 接客におけるルールやマナーも整理します。 例えば、「身だしなみ基準」「言葉遣い」「お客様との距離感」など、見えにくいルールこそ動画で視覚的に示すことで浸透しやすくなります。
- 3. 動画化する接客業務・ルールの決定
- すべての業務を動画にする必要はありません。動画にすることで理解が深まる業務、テキストでは伝えにくい業務を優先的に選定します。
例えば、来店時・退店時の声かけの仕方(声量・声のトーン、表情、距離感など)や「案内→注文→提供→会計」「声かけ→商品説明→試着対応→レジ対応」といった接客の流れなどが挙げられます。 - 4. 動画マニュアルの構成・台本の作成
- 一般的には、「本マニュアルの目的の説明→接客の実演→補足解説」といった流れで構成を組み立てます。ただし、対象者が集中して学べるように1つの動画あたりに含める情報量は必要なものに絞りましょう。
台本は、動画に登場するセリフやナレーション、カメラの動き、登場人物の行動、テロップ表示などを具体的にまとめた設計図です。具体的に作成することで、スムーズな撮影進行につながります。 - 5. 構成・台本に沿って動画の撮影
- 構成・台本が決定したら、撮影は実際の店舗で行いましょう。対象者は、自分の姿を出演者に重ねて視聴できるため、実際の接客イメージがわかりやすくなります。
接客マニュアルの場合には、見本となるスタッフの表情や姿勢、動作がわかるようなアングルから撮影することが重要です。スタッフに求めている接客が伝わる撮影を心がけましょう。 - 6. 撮影した動画編集
- 編集時には、字幕やテロップ、BGM、ナレーションなどを工夫し、対象者が直感的に理解できるようにします。
- 7. 社内へ共有
- 動画が編集できたら、まずは管理者や現場の担当者など複数人に見てもらい、実際の接客と合っているか確認しましょう。 確認できたら、社内に共有します。全員に共有することで、既存スタッフ全員の認識を均一化できます。
動画化に適した業務
実は、動画マニュアルはすべての業務に適しているわけではありません。
接客マニュアルを動画化する業務を決定する際には、動画化により効率的に理解を深められる、適した業務を選ぶことが大切です。ここでは、具体的に動画化に適した業務を解説します。
- 基本の挨拶
- 来店時や退店時のあいさつ、店頭での声がけなどのマナーは、動画化することで声のトーンや表情、姿勢なども視覚・聴覚を通して学習できます。
特に外国人スタッフや未経験者にとっては、見本を繰り返し確認できる基準となります。 - 接客の流れ
- 飲食店では、来店時の案内、オーダーの取り方、料理の提供、会計までの一連の流れが挙げられます。「どこで、どのように声かけするか」「動線をどう取るか」など、流れを可視化することで対象者の即戦力化を促進できます。
- 店舗運営に関わる業務
- 開店準備・閉店作業・清掃・備品の補充・レジ締め作業など、一定の手順がある業務も動画マニュアル化におすすめです。
特に機器の使い方やマニュアルに従った操作が必要な作業では、動画によって正確な手順を視覚的に共有できます。店舗独自の手順がある作業や特殊な器具・機械の操作については、注意点を動画マニュアルに組み込みましょう。
接客マニュアル動画作成と運用のコツ

動画マニュアルを効果的に活用するためには、「ただ作るだけ」で終わらせず、運用と改善の工夫が求められます。ここで紹介するコツを押さえることで、現場で役立つ接客マニュアルの作成につながります。
- 自社の方針を反映する
- 店舗・会社が目指すコンセプトやブランディングにより、求める接客内容は大きく異なります。
例えば、高級感を重視するホテルと、親しみやすさを売りにするカジュアルレストランでは、言葉遣いや立ち振る舞いに求められる内容も異なるでしょう。
見本となる動画マニュアルでの振る舞いや言葉遣い、動作にも自社の方針を反映させることで、教育だけでなく自社のブランディングにも役立ちます。 - 具体的な例を入れる
- 「この対応は良い例」「この言い方はNG」など、実際のシチュエーションを具体例として取り入れると、対象者の理解が深まります。
正しいやり方だけでなく、よくあるミスや避けるべき行動もあわせて示すことで、より実践的な内容になります。 - 定期的に見直し・改善を行う
- 業務フローの変更、設備の更新、サービス内容の変化などに伴い、マニュアルも定期的に更新する必要があります。
具体的には、半年〜1年に一度は内容を見直す機会を設けることがおすすめです。必要に応じて再編集・再撮影を行うことで、現場との乖離を防ぎます。
長く使える接客マニュアル動画のために
小売・飲食やサービス業では、新人教育や教育コストの削減、接客クオリティの改善が見込めるメリットから、接客マニュアル動画を活用する企業が増加しています。テキストでは伝わりにくい動作や振る舞いが重要な業務を動画化することで、より効率的に理解を深められるでしょう。
また、3つのコツを意識して作成することで、ただルールをまとめたものではなく、自社のブランディング構築や即戦力の新人を育てるのに有効な教材として長く使い続けられる接客マニュアルになるでしょう。
クリエイターの選定から依頼のやりとりを専任担当がサポート!
「自分でイラスト依頼のやりとりをするのが不安…」という方は、ぜひ「cone(コーン)」をご活用ください。
実際に、クリエイターの選定を行うのもなかなか大変… 「すぐに返信が来るかわからない…」「権利周りの相談で時間が掛かりそう…」など、商用利用では特にクリエイターへ依頼するまでに時間が掛かる事が多く、慣れていないと大変なんです…
そんな時は!
coneは法人企業からクリエイターへ依頼ができるサービス。
専任スタッフがクリエイターとのやりとりを代行し、納品までサポートします!
まずは、お気軽にご相談、お問い合わせください。
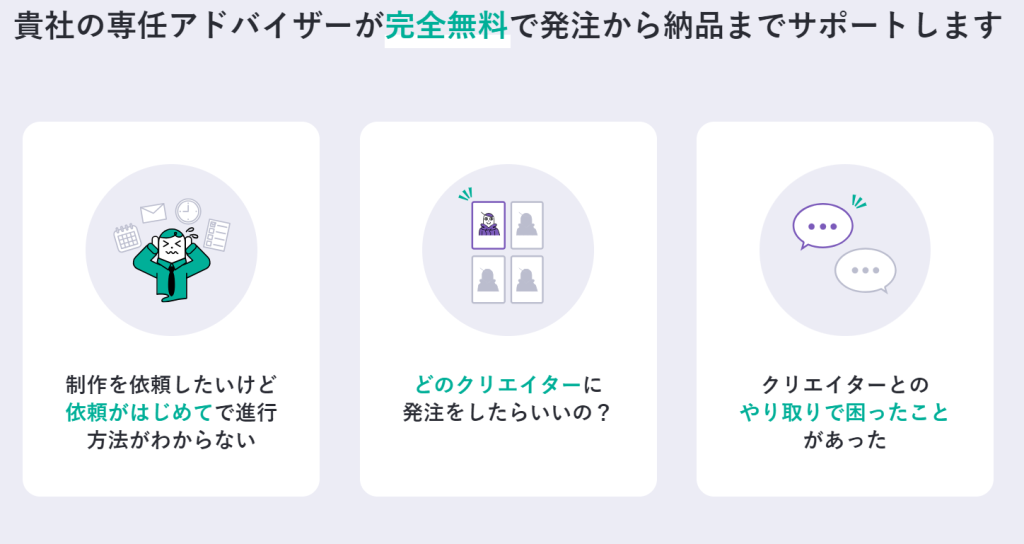
coneには、様々なニーズに対応できる実績豊富なプロのクリエイターが多数在籍しています。
ご希望の予算や納期に応じたご提案も可能です。
イラスト依頼のサポートや相談、「cone」の詳細をご希望の場合は、お気軽に「お問い合わせ」ください。