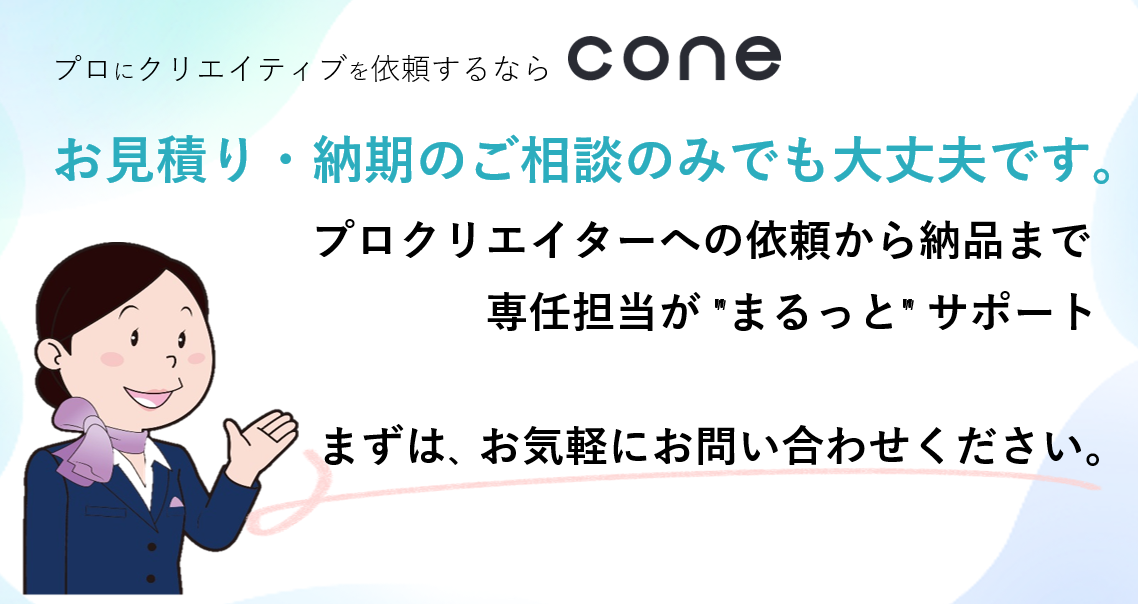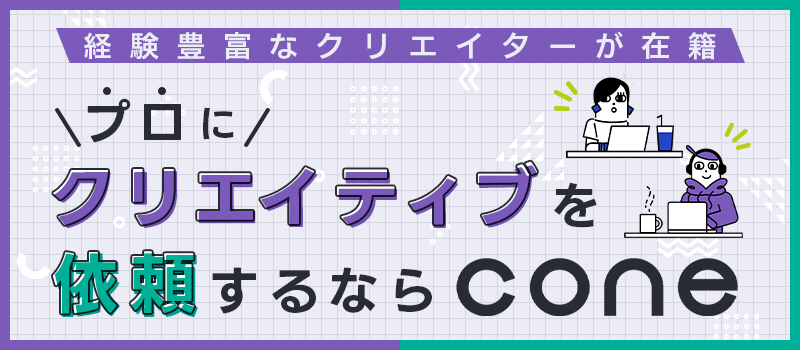製造業において「マニュアル」は、業務の標準化・品質管理・安全確保などに欠かせない存在です。従来は紙のマニュアルが主流でしたが、近年では「動画マニュアル」が注目を集め、導入する企業が増加しています。
しかし、なぜ今、製造業で動画マニュアルが求められているのでしょうか。その理由を理解することで、より質の高い動画マニュアルを作成できるでしょう。
そこで、本記事では、製造業におけるマニュアルの重要性や紙マニュアルとの違い、動画マニュアルが解消する課題、作成手順や方法についてわかりやすく解説します。
目次
製造業におけるマニュアルの重要性
製造業では、製品の品質や安全性のために、日々の業務を標準化することが求められます。業務の標準化に欠かせないツールが、マニュアルです。ここでは、製造業におけるマニュアルの重要性を解説します。
- 社員・会社の安全
- 製造現場では、重機・精密機器を使用した業務の手順漏れや操作ミスなどが、事故やケガ、機械の故障につながるリスクがあります。 正しい手順や操作をマニュアルで明文化・可視化し、従業員がマニュアル通りに作業することで、未然に事故を防ぎ、安全な職場環境を維持できます。
- 品質を一定に保つ
- 作業手順を詳細にまとめたマニュアルに基づいて作業を行うことで、個人差による品質のばらつきを減少させ、一定の品質に保ちます。
特に同一製品を大量生産する場合には、手順の統一は品質維持に欠かせないため、マニュアルの整備は必須です。
- 属人化の防止
- 作業のノウハウやコツをマニュアルとして社内で共有することで、作業の属人化を防ぎます。
例えば、ノウハウが一部のベテラン社員に属していると、退職や異動の際に業務に支障をきたすリスクがありますが、マニュアルによって知識を社内で共有していればスムーズな教育・引継ぎにつながります。
動画マニュアルと紙マニュアルの違い
近年取り入れる企業が増加している動画マニュアルと以前から活用されてきた紙のマニュアル、それぞれにメリット・デメリットがあります。ここではそれぞれのメリット・デメリットをまとめました。
| 紙マニュアル | 動画マニュアル | |
| メリット | ・すぐに参照でき、持ち運びや配布が簡単作成 ・修正が容易 ・特定の手順や数値などを一覧的に確認しやすい | ・視覚と聴覚を通じて直感的に理解できる ・実際の動作を見せることで複雑な工程もわかりやすい ・言語が苦手な人にも伝わりやすく、外国人労働者の教育にも有効 ・社内デバイスでアクセス権を付与すれば、場所・時間を問わず視聴できる |
| デメリット | ・動作や流れの説明には不向き ・読解力が必要で、理解に時間がかかりやすい ・情報が断片的になりやすく、記憶に残りにくい ・保存場所が必要になる ・長期間保管することで、劣化することがある | ・撮影、編集に時間とコストがかかる内容変更時には再編集が必要 ・視聴環境(端末・ネット回線など)に依存する部分がある |
このように、動画マニュアルと紙マニュアルには、それぞれメリット・デメリットがあります。内容によって、どちらの形態で作成するか決定しましょう。
動画マニュアルで解消できる製造業の課題

製造業において、自社製品の生産性や品質を高め、顧客に満足してもらうために、日々さまざまな課題解消に向けて取り組んでいることでしょう。動画マニュアルは、製造現場の業務改善と教育の省力化を実現する強力なツールとなるのです。
実は動画マニュアルの作成により、以下の3つの課題解消につながる可能性があります。
- 品質のばらつき防止
- 作業工程を動画で明示することで、誰が担当しても一定の品質を保ち、ばらつきの防止につながります。
ベテランの技術やノウハウを映像で可視化することで、新人でも一定の再現性をもった作業を実施できるようになります。 - 人的エラー・無駄な工程の削減
- 視覚的な情報で「どこをどう操作するのか」「何を省略してはいけないか」などを明確に共有できるため、不要な作業の削減や人的エラーの発生を抑制できます。
その際、注意すべきポイントにおいては、強調して撮影することが大切です。 - 教育工数の削減
- 教育担当者が口頭で何度も同じ説明を行う必要がなくなり、教育にかかる時間や人員を大幅に削減できます。
新人が自己学習できる環境を整えることで、教育の効率化とコスト削減につながります。
このように、動画マニュアルは、製造現場の業務改善と教育の省力化を実現する強力なツールとなるのです。動画マニュアルを活用し、製造業で発生しがちな課題の解消に役立てましょう。
製造業における動画マニュアル作成の流れ
製造業の動画マニュアルの作成は、以下のように作成の流れを順序立てて行う必要があります。
- 動画マニュアル作成の目的の明確化
- 製造プロセスから動画マニュアルに盛り込む工程のリストアップ
- 動画マニュアルの構成・台本の作成
- 構成・台本に沿って動画の撮影
- 撮影した動画編集
- 社内へ共有
製造業の動画マニュアルを作成する流れを把握することで、スムーズな進行が可能になるでしょう。動画マニュアル作成の流れの詳細は、以下の記事をご覧ください。
【要Check!】関連記事:動画マニュアルのメリットと作り方をわかりやすく解説
現場で使われる動画マニュアルにするための実践的な作成ポイント

動画マニュアルをせっかく作っても、現場で活用されなければ意味がありません。製造現場で実際に使われ、教育や業務改善に役立つ動画マニュアルに仕上げるための実践的なポイントを解説します。
- 対象者の目線に立って作成する
- 製造業では特に、「対象者目線」で内容を設計することが大切です。 新人やパート社員など、はじめて業務に携わる人でも理解できるように、専門用語を控え、作業の背景や目的をわかりやすく説明することが求められます。 また撮影時には、作業者の全体像だけでなく、手元が見えるようなアングルも撮影するなど、工夫しましょう。
- 一動画=一工程でシンプルに伝える
- 情報過多を避けるため、「1本の動画に1つの工程」に絞ることが重要です。複数の工程を盛り込むと理解が追いつかず、現場では使いづらくなってしまいます。 必要な情報にすぐアクセスできるように動画を分割し、目的別に整理しておくと、確認や再学習もスムーズになります。
- 字幕やテロップで視覚的な補足を行う
- 製造現場では、機械音や周囲の騒音の影響で音声が聞き取りづらい場面が多くあります。そのため、動画マニュアルには音声だけでなく、字幕やテロップによる視覚的な補足が欠かせません。作業の要点や注意点を画面上に文字で表示することで、音声が届かない環境でも内容が正しく伝わり、理解を深めることができます。 また、外国人労働者への対応として、多言語字幕を付けることで教育の幅も広がります。特に危険を伴う工程や間違えやすい手順などは、強調されたテロップで伝えると効果的です。 視覚・聴覚の両方から情報を伝えることで、誰にとっても理解しやすく、ミスや事故を未然に防ぐマニュアルが実現します。
- 現場の声を取り入れて改善する
- 現場での継続的な運用を目指すには、マニュアル完成後の改善も欠かせません。 現場における対象者の管理者や対象者本人からのフィードバックを収集し、「わかりにくい部分」「追加してほしい情報」などを取り入れてブラッシュアップしましょう。より実践的で使われる動画マニュアルに成長します。 また、新しい機器・設備、システムなどが導入された場合や作業工程に変更があった場合にも、都度更新する必要があります。
製造業向けの動画マニュアル作成方法
動画マニュアル作成の選択肢には、「自社で内製する方法」「個人クリエイターに依頼する方法」「動画制作会社に依頼する方法」の3つがあります。予定している作成期間や費用、社内リソースに応じて最適な方法を選びましょう。
- 自社で内製する
- 自社で動画マニュアルを内製する方法は、最もコストを抑えられる選択肢です。スマートフォンやデジタルカメラなどで撮影し、PowerPointや無料の動画編集ツール(例:iMovieやMicrosoft ビデオ エディター)を活用すれば、初期費用をほとんどかけずに動画を作成できます。
ただし、動画編集の知識が必要になるうえ、撮影・編集・ナレーション・構成など多くの工程を自社で担う必要があるため、時間と労力がかかります。担当者にスキルや経験があれば、費用対効果の高い手法といえるでしょう。 - 個人クリエイターに依頼する
- 動画制作にある程度のクオリティを求めつつ、コストも抑えたい場合は、個人クリエイターへの依頼がおすすめです。依頼費用は内容によって異なりますが、1本あたり5万〜20万円程度が相場です。
希望を伝えることで、比較的柔軟に対応してもらえることが多く、シナリオ作成から撮影・編集までを一貫して依頼できるケースもあります。ただし、個人クリエイターによってクオリティのばらつきが出やすいため、実績やポートフォリオを確認したうえで選定することが重要です。
また、個人クリエイターへの依頼は、契約後の音信不通や対応の不備などのトラブルが発生するリスクがあります。そのため、SNSなどで直接個人クリエイターとやり取りを進めるよりは、coneやココナラなどのクラウドソーシングサービスを介して個人クリエイターと契約した方が、トラブルを回避できる可能性が高まります。 - 動画制作会社に依頼する
- 高品質な動画マニュアルを安定的に制作したい場合は、専門の動画制作会社への依頼が適しています。撮影機材やナレーション、アニメーション、テロップ処理など、プロの技術で仕上げられるため、完成度の高いマニュアルが期待できます。
費用は制作内容によって幅がありますが、1本あたり30万円〜100万円以上となるケースもあります。また、制作までに一定の打ち合わせや企画期間が必要となるため、短納期での対応が難しい場合もあります。
関連記事:技術の継承に必須!実用的な建設業の動画マニュアル作りのポイント
クリエイターの選定から依頼のやりとりを専任担当がサポート!
「自分でイラスト依頼のやりとりをするのが不安…」という方は、ぜひ「cone(コーン)」をご活用ください。
実際に、クリエイターの選定を行うのもなかなか大変… 「すぐに返信が来るかわからない…」「権利周りの相談で時間が掛かりそう…」など、商用利用では特にクリエイターへ依頼するまでに時間が掛かる事が多く、慣れていないと大変なんです…
そんな時は!
coneは法人企業からクリエイターへ依頼ができるサービス。
専任スタッフがクリエイターとのやりとりを代行し、納品までサポートします!
まずは、お気軽にご相談、お問い合わせください。
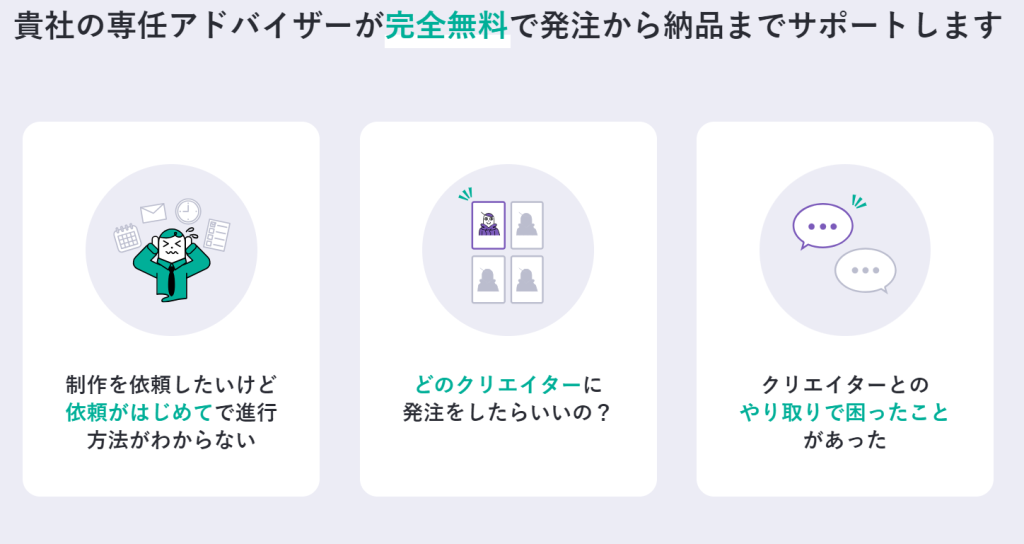
coneには、様々なニーズに対応できる実績豊富なプロのクリエイターが多数在籍しています。
ご希望の予算や納期に応じたご提案も可能です。
イラスト依頼のサポートや相談、「cone」の詳細をご希望の場合は、お気軽に「お問い合わせ」ください。