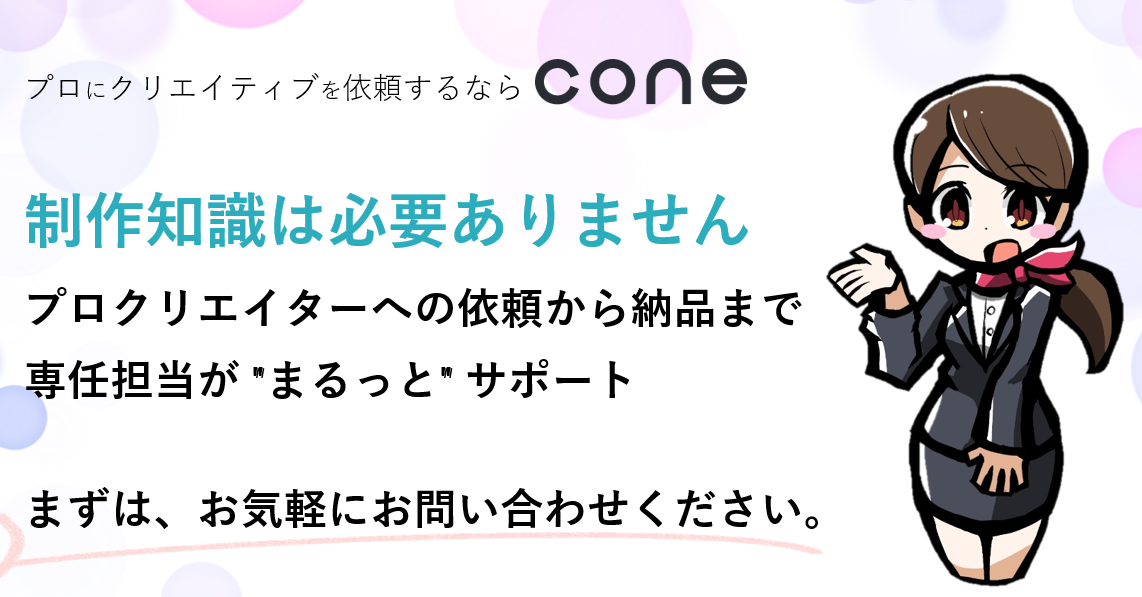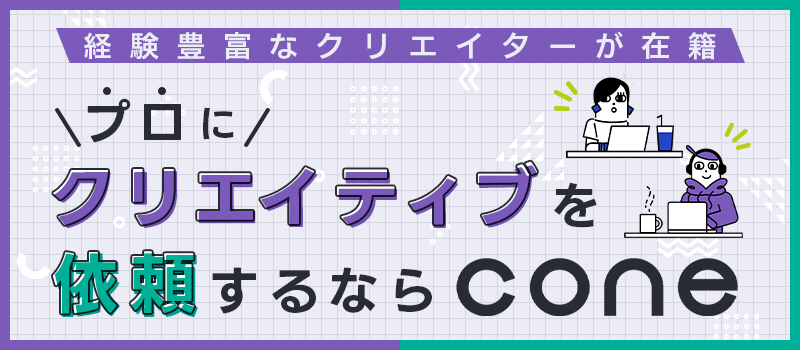建設業において、安全性の確保と技術の継承は、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。
これまで紙のマニュアルや口頭による伝承に頼っていた作業手順やノウハウの共有は、動画マニュアルの導入により、
よりわかりやすく、効率的に行えるようになってきました。
そこで、本記事では、建設業における動画マニュアルの特徴や導入メリット、
そして実用的な動画マニュアルを作るためのポイントと基本的な作成の流れを解説します。
目次
動画マニュアルの特徴
動画マニュアルとは、作業手順や機器の使い方などを映像で記録し、視聴者に対して視覚的・聴覚的に情報を伝えるマニュアルのことです。
最近では、建設業や製造業、接客業などを中心に動画マニュアルを導入する企業が増えています。
その理由は、従来の紙のマニュアルとは異なる特性を持っているためです。
動画マニュアルには以下のようなメリット・デメリットがあります。
- 視覚的理解のしやすさ:複雑な作業手順や動きが、実際の映像を通して確認できるため、理解が格段に向上します。
- 再現性の高さ:同じ内容を繰り返し確認できるため、習熟度に差がある新人でも、自分のペースで学習が可能です。
- 人数への同時教育が可能:1本の動画を複数人で共有することで、教育の均質化が図れます。
- 作成に時間や手間がかかる:撮影・編集・シナリオ作成など、動画制作には一定のリソースが必要です。
- 更新の度に手間がかかる:作業手順の変更があった場合、動画を再編集または再撮影する手間が発生します。
- データ容量や閲覧環境への配慮が必要:高画質の動画は容量が大きいため、共有・保管方法にも注意が必要です。
動画マニュアルのメリット・デメリットを踏まえ、自社の教育方針やリソース、閲覧環境などに適しているかを見極めることが大切です。
建設業で動画マニュアルを導入するメリット
建設業で動画マニュアルを導入することで、「工事現場の安全性の向上」や「技術・ノウハウの継承」「現場以外でも機械の操作などを学習しやすくなる」といったメリットを生みます。

現場の安全性
建設現場では、高所作業や重機の操作など、一歩間違えば重大な事故につながる作業が日常的に行われることから、従業員の安全確保は非常に重要です。
その際、紙のマニュアルでは伝えにくい現場作業の動作・手順や注意点を動画で明示できるため、作業員が事前にリスクを把握しやすくなります。
作業員が共通の認識をもって作業にあたることで、職場全体の安全性の確保につながります。
また、共通の動画マニュアルを活用することで、指導者ごとのばらつきや誤解のリスクも軽減されます。
技術・ノウハウの継承
建設業では、長年現場で培われたベテラン職人ならではの知識やスキル、ノウハウを伝承することが不可欠です。
紙にこうした技術・ノウハウを書き起こすのは困難ですが、動画であれば職人の熟練した手の動きや注意の仕方など、細かなニュアンスまで記録することが可能です。
また、動画を教材として蓄積すれば、ベテラン職人の知見を若手職人にスムーズに共有できます。
人から人に直接伝えるやり方は、多くの時間をかけた1対1の指導が必要ですが、実際の動きを撮影し動画化することで、一度の時間で多くの職人への伝達が可能になります。
現場以外での学習が可能
建設業では、現場の忙しさや安全上の制限から、現地でのOJTだけに頼ることは困難な場合があります。
その点、動画マニュアルであれば、タブレットやスマートフォンなどの端末から、休憩時間や自宅などで場所や時間を選ばずに学習できる点が大きな魅力です。
繰り返し視聴できることから、指導された内容の予習や復習にも活用でき、教育の効率化にもつながります。
建設業の動画マニュアル作成の基本的な流れ
建設業の動画マニュアルは、「動画化する作業の決定→構成の作成→実演者の選定→動画撮影→動画編集」という流れで作成します。
ここで解説する建設業の動画マニュアルを作成する流れを把握することで、スムーズな進行が可能になるでしょう。
動画化する作業の決定
まずは、どの作業を動画化するかを選定します。
新人教育で使用する基本作業や、事故が起きやすい要注意作業、特殊機械の操作など、「誰に・何を教えるための動画か」を明確にしたうえで選定しましょう。
動画マニュアルに適している「動きや判断を伴う業務」「安全性が問われる業務」「繰り返し見ることで技術習得が進む業務」といった観点から検討すると、例えば以下のような内容が動画化に適しています。
- 重機・建設機械の操作手順
- 足場の組立・解体手順
- 塗装・防水・左官などの仕上げ作業
- 安全帯・保護具の着用手順・点検手順
動画化する内容を絞ることで、撮影や編集の負担を軽減し、より精度の高い動画を作成できます。
構成の作成
作業工程を洗い出した後は、動画の構成を作成します。
「作業の目的や準備物を伝える→手順や注意点を解説→復習や確認事項を入れる」といった構成が一般的です。
この段階でナレーションやテロップの内容も決めておくことで、撮影での撮り忘れを防ぎ、かつ、撮影後の編集作業がスムーズになります。
実演者の選定
動画に登場する実演者は、作業の正確性だけでなく、見本として他の作業者に模倣される存在となります。
技術力の高いベテランや、説明しながら作業できる人材を選びましょう。
また、撮影時の服装や安全装備にも配慮し、「手本としてふさわしい」状態を整えることが重要です。
動画撮影
撮影は、実際の現場で行うのが理想です。リアルな環境を映すことで視聴者の臨場感が高まり、実践的な学びにつながります。
また、三脚やジンバルを使った安定した撮影、複数のアングルを用いた編集素材の確保など、視認性の高い映像を撮るための工夫が必要です。
動画編集
撮影した映像をもとに、必要な部分だけを残す編集作業を行います。冗長な部分はカットし、要点を短時間で伝えられるように編集します。
加えて、ナレーションや字幕を挿入し、特に注意すべき箇所には強調を加えることで、伝わりやすさが向上します。
完成した動画は、見やすさと理解しやすさを意識した長さ(3〜10分程度)にまとめるのが理想的です。
実用的な建設業の動画マニュアルを作るポイント
実用的な建設業の動画マニュアルを作成するためには、マニュアルの作成と運用において、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

動作を確認しやすい映像
建設現場では、手順の中に危険を伴う動作が多く存在するため、正しい操作や判断ができるようにすることが重要です。
そのためには、視聴者が動作を正確に確認できる映像である必要があります。
例えば、重機の操作や電動工具の使用といった場面では、実際に手元の動きが見えるようにカメラアングルを工夫する必要があります。
クローズアップで操作部分を見せるカットを入れたり、複数のカメラを使って全体像と詳細部分を並行して見せたりするなど、視聴者の理解を促す工夫が求められます。
また、実際の現場音がある場合は、ナレーションやテロップによる補足で誤解を防ぐといった配慮も重要です。
現場でのヒアリング
ベテラン作業員の動きには、長年の経験から自然と身に付いた工夫や注意点が含まれていることが多く、本人がその重要性を自覚していない場合もあります。
そのため、マニュアル作成にあたっては、実演前後に現場でのヒアリングを行い、なぜその動きをしているのか、どういった注意点があるのかを言語化する作業が欠かせません。
これにより、経験に基づく「暗黙知」が言語で表現される「形式知」へと変換され、後輩世代にも伝わりやすくなります。
ヒアリング内容はナレーションや補足説明に反映することで、より実用的な動画になります。
視聴環境の整備
せっかく動画マニュアルを作っても、必要なタイミングで視聴できなければ動画化のメリットを十分に享受できません。
特に、建設業では屋外や通信環境の悪い現場で働くことも多いため、オフラインでも視聴可能な環境を整えることが大切です。
例えば、スマートフォンやタブレットへの事前ダウンロードが可能なアプリを利用したり、社内で共有できるクラウド環境を用意したりすることで、いつでも動画にアクセスできる体制を整備することが求められます。
また、動画を探しやすいように目次機能やキーワード検索などを活用できるソフトを導入することも、日常的に使われる動画マニュアルを作成するポイントといえるでしょう。
関連記事:動画マニュアルが解消する製造業の課題とは?作成の流れも解説
クリエイターの選定から依頼のやりとりを専任担当がサポート!
「自分でイラスト依頼のやりとりをするのが不安…」という方は、ぜひ「cone(コーン)」をご活用ください。
実際に、クリエイターの選定を行うのもなかなか大変… 「すぐに返信が来るかわからない…」「権利周りの相談で時間が掛かりそう…」など、商用利用では特にクリエイターへ依頼するまでに時間が掛かる事が多く、慣れていないと大変なんです…
そんな時は!
coneは法人企業からクリエイターへ依頼ができるサービス。
専任スタッフがクリエイターとのやりとりを代行し、納品までサポートします!
まずは、お気軽にご相談、お問い合わせください。
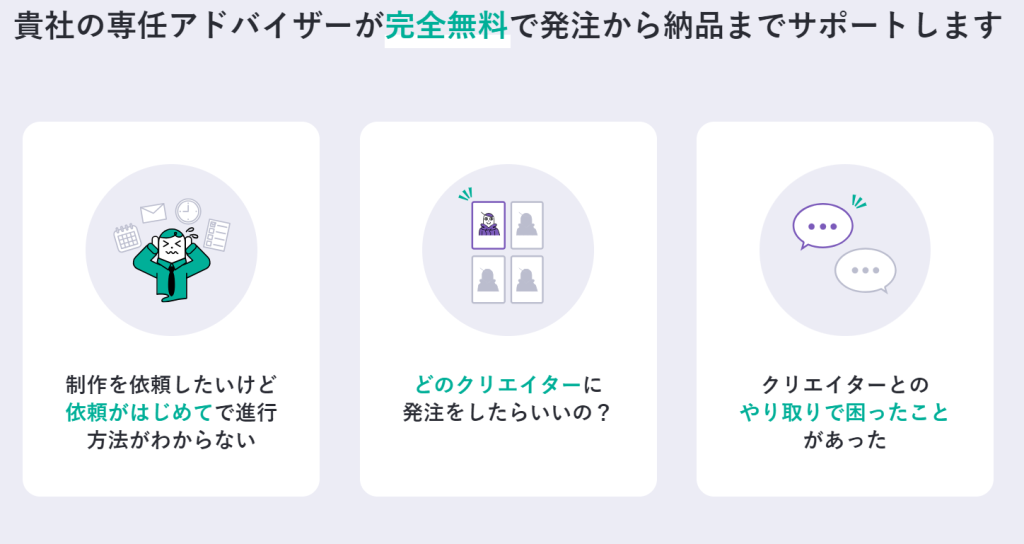
coneには、様々なニーズに対応できる実績豊富なプロのクリエイターが多数在籍しています。
ご希望の予算や納期に応じたご提案も可能です。
イラスト依頼のサポートや相談、「cone」の詳細をご希望の場合は、お気軽に「お問い合わせ」ください。