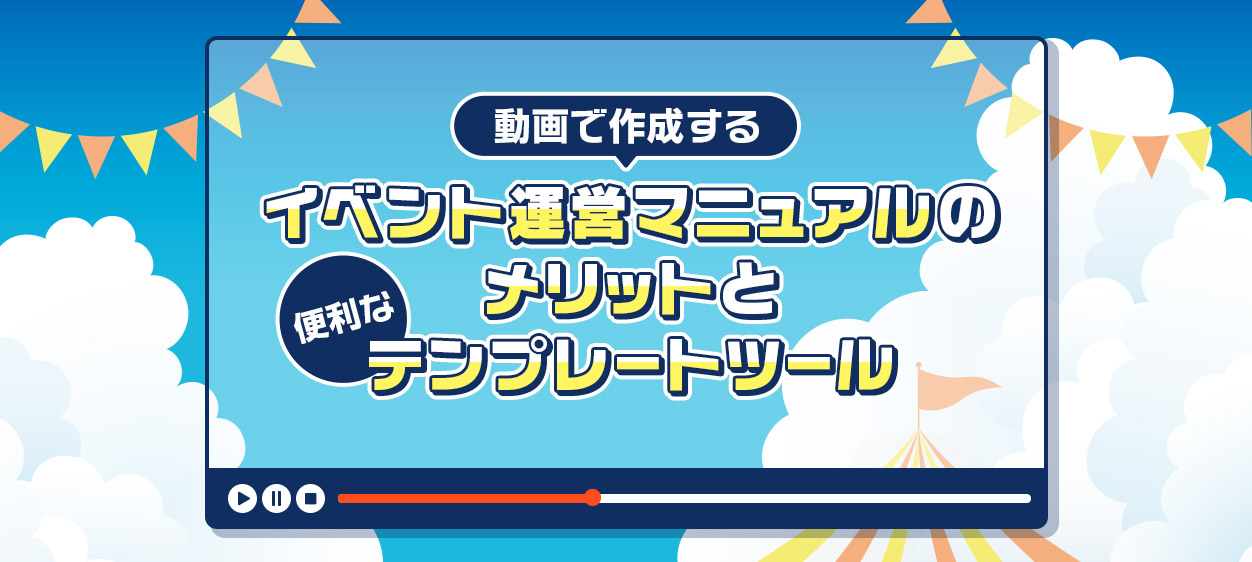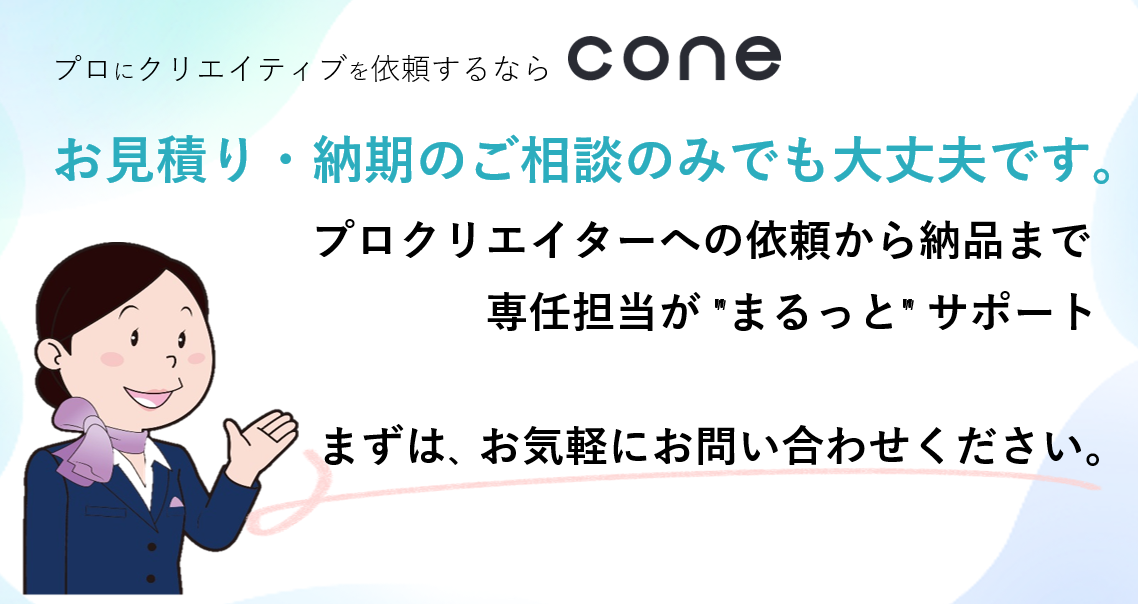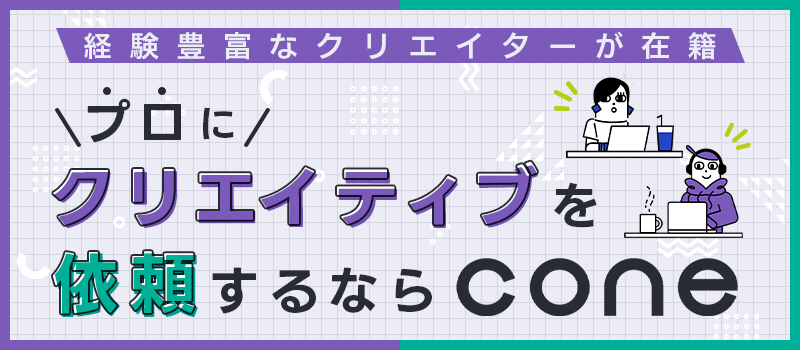イベントの成功には、関係者全員が同じ方向を向いて動くことが不可欠です。
しかし、イベントの準備・運営では、多数のスタッフがさまざまな業務内容に従事することから、口頭や紙の指示だけでは情報伝達が曖昧になりがちです。特に初参加のスタッフやアルバイトにとっては、どのタイミングで何をすべきかを瞬時に理解するのは容易ではありません。
こうした課題を解決する手段として注目されているのが、「動画による運営マニュアル」の活用です。
そこで、この記事ではイベント運営における動画マニュアルの重要性やマニュアルテンプレートツールを紹介します。
目次
イベント運営における動画マニュアルの重要性
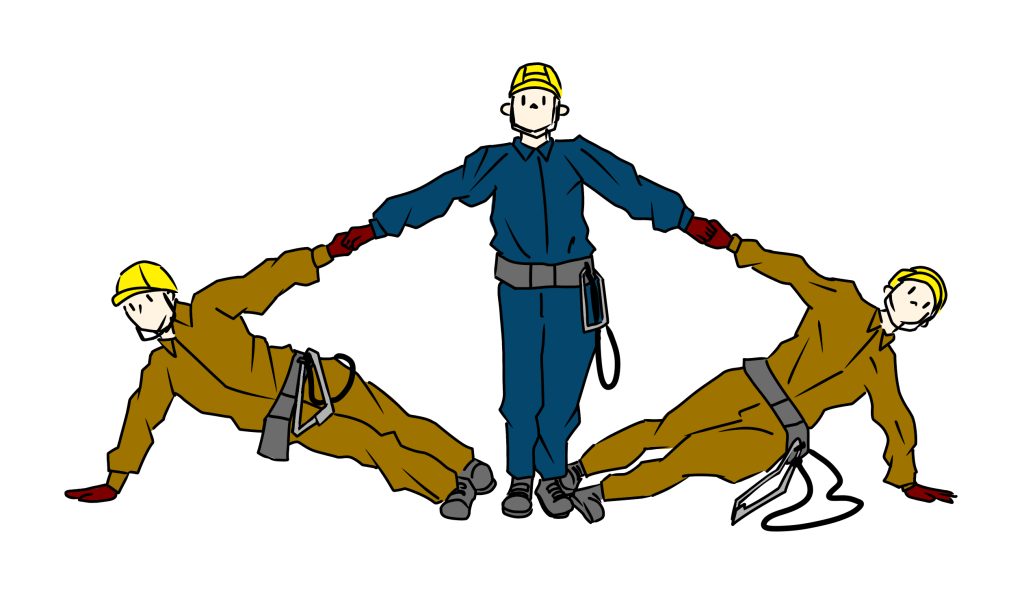
イベント運営において、参加者やスタッフ、関係者との情報共有は欠かせない業務の一つです。特に準備・設営・当日の進行など、多岐にわたる作業をスムーズに進めるためには、明確な手順書やマニュアルの整備が必要不可欠です。
そこで近年注目されているのが、動画によるイベント運営マニュアルの作成です。動画であれば、作業手順や動きのある内容も視覚的に分かりやすく伝えられるため、はじめてイベントに関わる人でも短時間で理解できる利点があります。
ここでは、イベント運営における動画マニュアルの必要性を解説します。
- 紙マニュアルで起こりがちなトラブル・リスクを防ぐ
- まず、マニュアルといって多くの人が思い浮かべるのは紙のマニュアルでしょう。
しかし、紙のマニュアルや文書ファイルは情報量が膨大になりがちで、「読み手によって理解度に差が出る」「持ち運びの不便さ」「現場での検索性の低さ」といった課題があります。
例えば、「設営時にどの機材をどこに配置するか」「来場者対応のフロー」などを確認したいとき、紙のマニュアルでは読んでもイメージが湧かず、現場での判断ミスにつながるケースも少なくありません。
動画マニュアルであれば、運営にかかる作業の全体像や作業の細部、当日の進行までを視覚的に理解できます。そのため、紙マニュアルに起こりがちなトラブル・リスクの防止につながります。 - 視聴者のモチベーション・集中力を維持できる
- 動画マニュアルでは「伝えたいことを強調できる」特長があります。 ナレーションにより手順や注意点を的確に伝えられ、BGMを加えることでリズム感が生まれ、視聴者の集中力が持続しやすくなります。 特に、日頃から動画を見る習慣がある若年層が多い場合には、動画マニュアルの方が視聴するモチベーションを高められるでしょう。
- 復習したい部分を手軽におさらいできる
- YouTubeなどのプラットフォームを使えば、チャプター機能や「〇分〇秒から再生」などの頭出し機能を活用できます。 これにより、「受付方法だけを確認したい」「撤収作業の要点だけを見たい」といった場合に、必要な部分だけをすぐに見返し、おさらいすることが可能になります。
- 1. 動画の「目次」を考えてから作成しよう
- 視聴者にとって、「必要な情報をどのファイル・どの部分から得られるか」が明確であることが重要です。
事前に動画の全体構成(目次)を設計することで、「受付編」「設営編」「撤収編」など、章立てされたわかりやすい動画を作成できます。
視聴者は自分が必要なシーンだけをチェックできるだけでなく、動画マニュアルを更新・編集する際にも該当部分をスムーズに検索でき、業務効率化につながります。 - 2. 1つのシーンに情報を詰め込みすぎない
- テンプレートは便利な反面、つい情報を盛り込みすぎてしまう可能性があります。 1つのシーンに複数の手順や説明を詰め込んでしまうと、視聴者はどこに注目してよいか分からなくなり、理解しにくい動画になってしまいます。 「1シーン1メッセージ」を意識して、テンポが良く、シンプルな編集を心がけましょう。
- 3. BGMを効果的に使用しよう
- BGMは、動画の雰囲気や視聴体験を左右する重要な要素です。
テンプレートツールにはあらかじめBGMが用意されていることが多く、シーンに応じて音楽を使い分けることで、動画にリズムやプロフェッショナル感を与えることができます。
ただし、BGMの音量が大きかったり、不要なBGMをつけたりすると、視聴者の集中力を損なう可能性があります。視聴しやすさを意識し、ナレーションや解説を邪魔しないようにBGMの有無や音量を決定することが大切です。 - 4. イラストを多用しよう
- 文字情報だけでは伝わりにくい内容も、イラストや図解を使えば一目瞭然です。テンプレートツールの多くには、アイコンやイラスト素材が用意されており、場面説明や注意喚起に役立ちます。
特に、外国人スタッフや未経験者が多い現場では、文字よりもイラスト中心の説明が効果的です。文字情報と組み合わせて、誰もが理解しやすい動画マニュアルを目指しましょう。 - 字幕の自動生成機能
- イベント現場は騒音が多く、音声が聞き取りづらいことも考えられます。そうした場面では、字幕機能が役に立ちます。音声を出せない環境にいても、文字情報で内容を把握できるため、視聴時のストレスや伝達漏れの防止につながります。
最近の動画編集ツールの多くには「音声から自動で字幕を生成する機能」があり、編集の手間を大幅に削減できるでしょう。 - QRコードによる共有機能
- QRコード共有機能は、作成した動画マニュアルをQRコードに変換して、スマートフォンやタブレットから読み取ることで、動画マニュアルを共有できる機能です。
作成した動画を簡単に共有できる仕組みとして、QRコードによる共有は有効な手段の一つです。都度、スタッフに「動画のURLを探して送る」といった負担がかからず、迅速な情報共有につながります。
例えば、印刷物や掲示物にQRコードを貼っておけば、イベント会場で突発的に発生した業務の確認や、設営中の作業手順のおさらいも可能です。 - カリキュラム機能
- 複数の動画を順を追って視聴してもらいたい場合は、カリキュラム機能のあるツールが便利です。「1本目の動画を見終えたら次へ進む」といった流れを設計できるため、教育や研修用にも適しています。
例えば、「設営の流れ → 来場者対応 → 緊急時対応」や「未経験者向け→一般実務者向け→管理者向け」などのように、段階的に情報を習得させたい場合にはカリキュラム機能はおすすめです。 - オフライン再生対応機能
- インターネット接続が不安定な屋外イベント会場や地下会場などでは、オフライン再生対応の有無が重要です。ツールによっては動画を端末にダウンロードしておけば、インターネットがない環境でも動画マニュアルを再生できます。
現場での実用性を重視する場合には、オフライン対応の有無は必ずチェックしましょう。 - 視聴記録のデータ化機能
- 社内研修や業務教育の一環として動画マニュアルを使う場合、「誰がどこまで視聴したか」という履歴をデータとして記録・確認できる機能があると安心です。スタッフの学習状況や習熟度を把握できるだけでなく、見落としや未視聴者へのフォローも容易になります。
特に複数人が関わるイベントでは、情報伝達の確実性を高めるうえでも有効です。 - VideoTouch(ビデオタッチ)
- AIの強力サポートで字幕やナレーションを自動生成可能
- 視聴分析やテスト機能により、学習進捗や理解度を把握できる
- コンタクトセンターに特化した機能が豊富
- VideoStep(ビデオステップ)
- 非IT部門でもパワーポイントやエクセルを触る感覚で動画作成が可能
- 動画の更新・改訂に関する履歴の記録が可能
- YouTubeのような検索性の高さ
- abiliclip(アビリクリップ)
- 生成AIによる自動翻訳機能により50言語以上に対応
- 現場の業務改善から経営変革の支援までを伴走支援
- 映像制作専門チームによるコンテンツ制作の支援の実施
- Teachme Biz(ティーチミー・ビズ)
- クラウド上でのマニュアル一元管理
- 多言語対応・字幕挿入可
- 閲覧履歴の可視化で教育効果を検証可能
- tebiki(テビキ)
- 自動字幕生成、音声読み上げに対応
- オフライン対応で現場での視聴もスムーズ
- レポートで学習の進捗状況を可視化可能
- cocomite(ココミテ)
- マニュアルの作成は「ドラッグ&ドロップ」中心で直感的
- 動画・画像・PDF・表組みなどを柔軟に組み合わせ可能
- 閲覧制限、アクセスログなどの管理機能も充実
テンプレートツールを使って作成するときのポイント
イベント運営における動画マニュアルを作成するとなると「何から始めたらいいか分からない」「編集スキルがなくて不安」という方も多いのではないでしょうか。
そうした場合には、動画テンプレートツールの活用がおすすめです。最近では、テンプレートツールを活用することで、簡単な操作感で、誰でもプロ品質のマニュアル動画を作成できるツールが多数登場しており、業務負担の軽減にもつながります。
ここでは、テンプレートツールを使って動画マニュアルを作成する際に押さえておきたい4つのポイントをご紹介します。
関連記事:動画マニュアルのメリットと作り方をわかりやすく解説
動画マニュアルを作成できるテンプレートツールの選び方
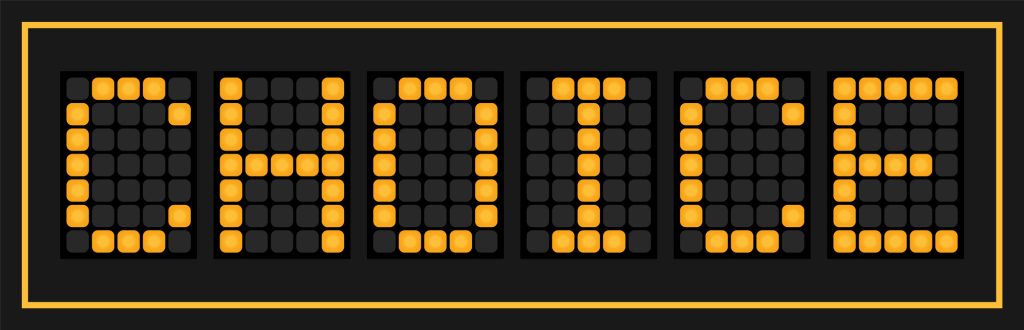
動画マニュアルを作成するうえで、テンプレートツールの活用は非常に有効です。ただし、ツールによって操作性や機能、導入コスト、対応デバイスなどの特徴や適性が異なるため、自社の運用体制や現場環境に合ったものを選ぶことが大切です。
ここでは、動画マニュアル用テンプレートツールを選ぶ際に注目すべき5つのポイントとして、現場で視聴する際に有効な機能を解説します。
【編集担当おすすめ】動画テンプレートツール6選!
動画マニュアルの作成には、多機能で使いやすいテンプレートツールの活用がおすすめです。
ここでは、編集担当が厳選した6つのツールを「有料版のみ提供しているもの」「無料体験版があるもの」に分けて紹介します。各ツールの特徴や強みを参考に、導入検討に役立ててください。
【有料版のみ】本格的な運用に適した3選
ここでは、有料版のみの3つの動画マニュアル作成ツールを紹介します。
AIによる強力なサポートを受けながら動画作成を実施できる動画作成ツールです。動画作成だけでなく、AIロールプレイング機能を設けていることで、視聴者の知識習得と実践をトータルサポートしています。
【おすすめポイント】
VideoStepは、製造業や飲食、小売など現場オペレーションの可視化に強みを持つ動画マニュアル作成ツールです。スマホ1台で撮影・編集・共有が可能であるため、はじめて動画マニュアルを作成する人でも、短時間でマニュアル化が実現できます。
【おすすめポイント】
abiliclipは、動画を介した双方向コミュニケーションが可能な動画マニュアル作成ツールです。各店舗や個人がもつ「暗黙知」を「形式知」へと転化するサイクルを高速に回すための現場作業に特化して設計されており、教育の標準化や業務の属人化解消に活用されています。
【おすすめポイント】
【無料体験版あり】まずは試せる3選
ここでは、無料体験版を提供している3つの動画マニュアル作成ツールを紹介します。
Teachme Bizは、企業・団体向けの業務マニュアル作成に特化したツールです。 画像や動画をステップ形式で構成でき、現場での「分かりやすさ」を重視した設計が特徴です。スマホやタブレットでの操作性に優れ、現場スタッフが簡単に閲覧・共有できます。
【おすすめポイント】
業務ノウハウを可視化し、人材のスキルデータと連携させ、作業・教育・評価の標準化を目指す動画作成ツールです。スマートフォンだけで撮影・編集・共有が完結し、直感的な操作性が人気です。
【おすすめポイント】
わかりやすさ・使いやすさを強みとするクラウド型のマニュアル作成・共有プラットフォームです。基本レイアウトに沿って入力するだけで、わかりやすいマニュアルを簡単かつスピーディーに作成できます。特に、ITが苦手なスタッフでも扱いやすい操作性が魅力です。
【おすすめポイント】
クリエイターの選定から依頼のやりとりを専任担当がサポート!
「自分でイラスト依頼のやりとりをするのが不安…」という方は、ぜひ「cone(コーン)」をご活用ください。
実際に、クリエイターの選定を行うのもなかなか大変… 「すぐに返信が来るかわからない…」「権利周りの相談で時間が掛かりそう…」など、商用利用では特にクリエイターへ依頼するまでに時間が掛かる事が多く、慣れていないと大変なんです…
そんな時は!
coneは法人企業からクリエイターへ依頼ができるサービス。
専任スタッフがクリエイターとのやりとりを代行し、納品までサポートします!
まずは、お気軽にご相談、お問い合わせください。
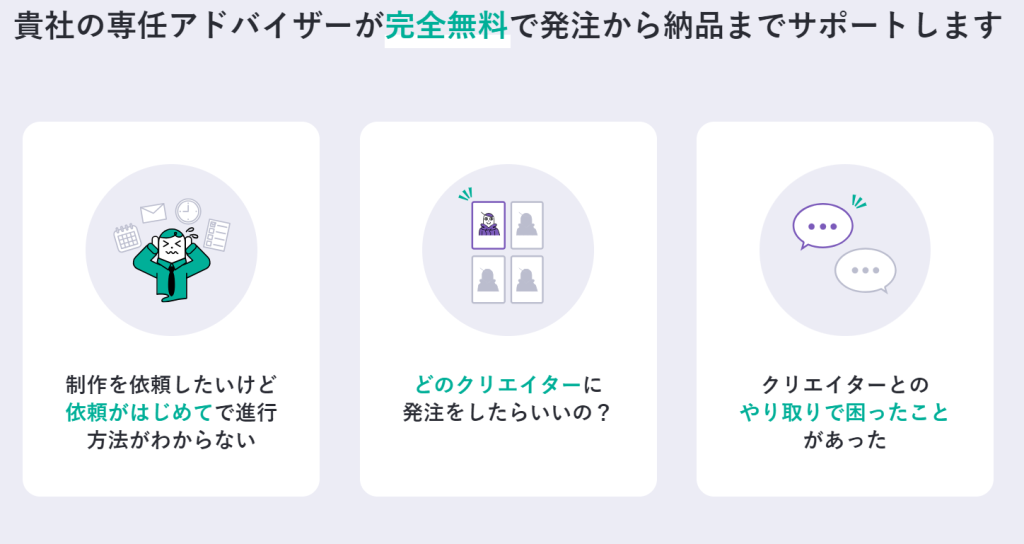
coneには、様々なニーズに対応できる実績豊富なプロのクリエイターが多数在籍しています。
ご希望の予算や納期に応じたご提案も可能です。
イラスト依頼のサポートや相談、「cone」の詳細をご希望の場合は、お気軽に「お問い合わせ」ください。