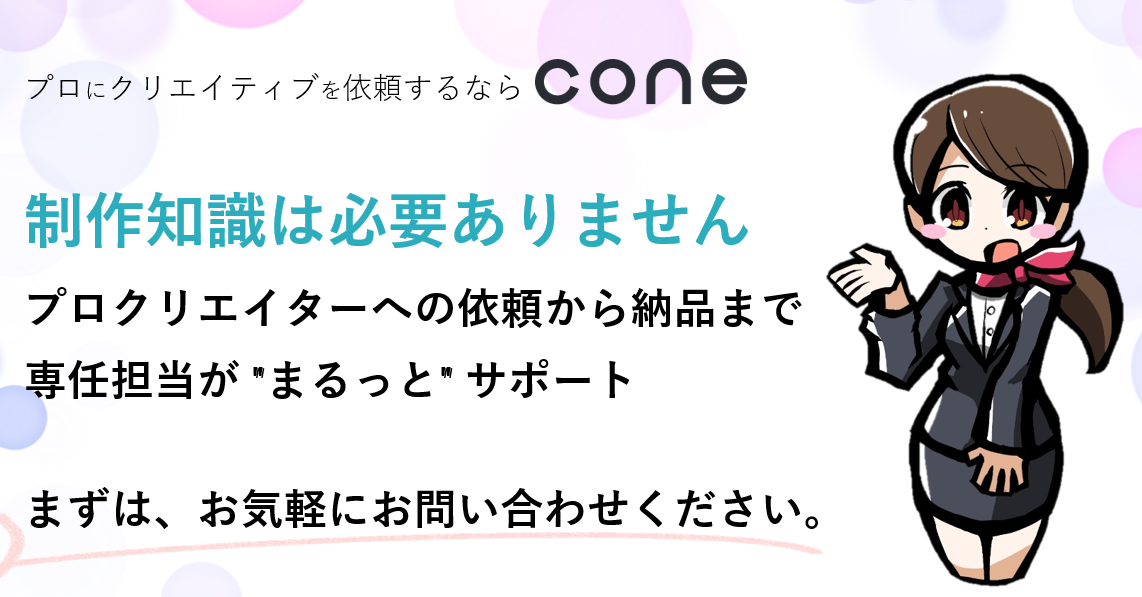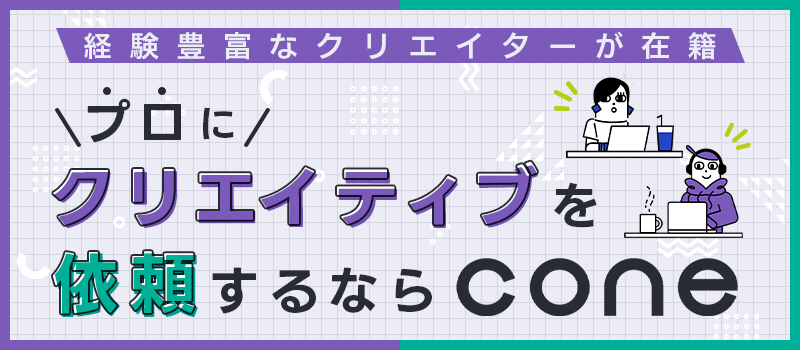広告やプロモーション動画、店頭POP、ゲームコンテンツなどで活用されるキャラクターデザインは、外部のデザイナーに依頼することで専門的な表現力を取り入れられるだけでなく、ブランドイメージの向上や販促効果の強化にもつながります。
ただし、依頼先が「フリーランスのデザイナー・イラストレーター」「制作会社」のどちらかなのかによって、料金体系や相場、著作権の取り扱い、契約条件には大きな違いがあります。限られた予算の中で効果を最大化するには、依頼先の特徴を理解して選択することが大切です。
そこで、本記事ではキャラクターデザインの制作工程を整理したうえで、フリーランスと制作会社に依頼した場合の費用相場や著作権の取り扱いの違いを詳しく解説します。外部デザイナーへの依頼を検討されている企業担当者や個人事業主の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
【外部依頼】キャラクターデザインの制作プロセス
キャラクターデザインを外部に依頼する際には、完成までにいくつかの工程を踏む必要があります。工程を理解しておくことで、制作会社やフリーランスのデザイナー・イラストレーターに依頼したときに、スムーズに案件を進めやすくなります。
ここでは一般的な制作プロセスを解説します。
1. 制作指示書の作成
まずは依頼内容を整理し、制作指示書を作成します。指示書には以下の内容をまとめておくと、スムーズな依頼につながります。
- キャラクターの利用目的(広告・動画・POP・ゲームなど)
- キャラクターのイメージや参考資料
- 使用範囲や著作権の扱い
- 予算・納期の目安
これらを明確にすることで、デザイナー・イラストレーターに正確に意図を伝えられ、不要な修正や費用の増加を防げます。
2. デザイナーとの打ち合わせ・ヒアリング
制作指示書をもとに、フリーランスや制作会社の担当デザイナー・イラストレーターと打ち合わせ・ヒアリングを行います。
- キャラクターの方向性や世界観の共有
- デザインの表現手法や制作工程の確認
- 相場を踏まえた料金の見積もり提示
この時点で作業内容の詳細や料金の見積もりが提示されるため、依頼主は内容を比較・検討することが大切です。
3.見積もり確認・契約を締結する
デザイナー・イラストレーターとの打ち合わせを経て、制作内容が固まったら最終的な見積もりを確認します。依頼料や制作範囲、納期に同意した段階で、契約を正式に締結する流れとなります。
契約を適切に締結しておくことで、依頼主とデザイナー・イラストレーターの双方にとって責任範囲が明確になり、トラブルを回避できます。特に法人企業や個人事業主が外部依頼する場合、著作権や費用の条件を文書化しておくことが重要です。
4. ラフデザイン案の確認・修正
契約締結後、デザイナー・イラストレーターはラフデザイン案を作成し、依頼主に提出します。キャラクターの雰囲気や方向性を決定する工程であるため、丁寧に確認する必要があります。
修正したい点がある場合には、契約時に決めた回数や範囲、タイミングに則って修正指示を行いましょう。明確に修正点や理由、改善イメージを伝えることが重要です。
5. 納品
ラフデザインの確認・修正を経て、最終的なキャラクターデザインが完成すると、納品が行われます。納品は、契約で定めた形式や範囲に沿って行われるため、事前に取り決めた内容を再確認しておくことが重要です。
【関連記事】:VTuber立ち絵の依頼手順を詳しく解説!相場と注意点も紹介
キャラデザ依頼で押さえておきたい制作会社とフリーランスの違い
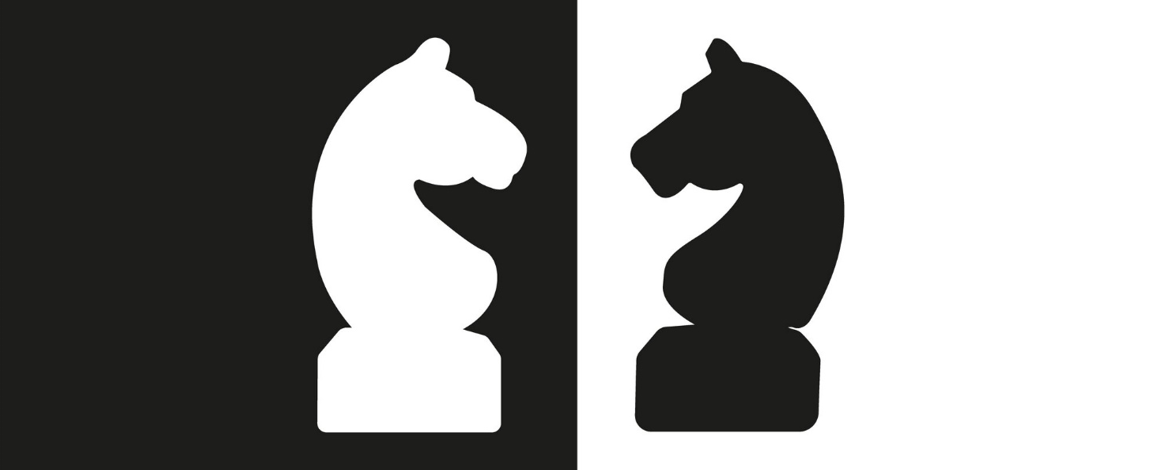
キャラクターデザインを外部に依頼する場合、依頼先として制作会社かフリーランスかで、費用や契約内容、制作体制、リスクの管理方法が大きく異なります。どちらにもメリット・デメリットがあるため、案件の規模や目的、納期、予算に応じて最適な選択をすることが重要です。
ここでは、法人企業や個人事業主がキャラクターデザインの外部依頼を行う際に、知っておきたい両者の違いを解説します。
案件に関わる人数と制作体制の違い
キャラクターデザインを外部に依頼する場合、案件に関わる人数や制作体制は依頼先によって異なります。
- 制作会社:複数のデザイナー・イラストレーターやスタッフが分担して制作するため、納期や品質の安定性が比較的高いです。
- フリーランス:担当者が一人で進めるため、小回りが利き柔軟な対応が可能ですが、急なスケジュール変更や担当者の都合に左右されるリスクがあります。
デザインを依頼する際は、納期や進行管理のしやすさと柔軟性のバランスを考え、どちらが自社案件に適しているかを判断するとよいでしょう。
トラブル発生の傾向と発生時の対応の違い
キャラクターデザインの制作依頼では、依頼主として「トラブルを防ぐこと」と「万一発生した場合に適切に対応できること」が重要です。制作会社とフリーランスでは、トラブルの傾向や対応方法に違いがあります。
- 制作会社:制作会社に依頼すると、基本的に会社が責任を負います。そのため、契約内容や補償、対応フローが比較的明確に整備されており、トラブルが発生しても対応がスムーズであることが一般的です。
- フリーランス:フリーランスに依頼すると、責任は個人デザイナー・イラストレーターが負います。最悪の場合、音信不通になるケースもあるため、依頼主は信頼できるデザイナー・イラストレーターかどうか見極めることが重要です。
どちらに依頼する場合でも、契約書で納期や修正回数、費用、著作権の範囲を明確に取り決め、万一トラブルが発生した際の対応フローを事前に確認しましょう。
請求書・インボイス対応など税務上の違い
請求書・インボイス対応など税務上の処理も、依頼先によって異なります。
- 制作会社:法人として請求書やインボイス対応が整備されている場合が多く、経理処理が比較的スムーズです。
- フリーランス:個人事業主として請求書やインボイスを発行可能ですが、事前に対応状況を確認しておく必要があります。
依頼主としては、支払い手続きや税務処理の負担を考慮して、適切な依頼先を選ぶことが重要です。
NDAや秘匿義務に関するリスクの違い
広告やゲーム、プロモーション動画などの案件では、企業が扱う情報の機密性が非常に重要です。
- 制作会社:情報管理やNDA(秘密保持条項)対応に関する内容の確認が、打ち合わせ時の説明フローや契約書に盛り込まれていることが多くあります。
- フリーランス:デザイナー・イラストレーターによって情報管理に対する対応が異なります。契約書にNDAを必ず盛り込み、情報の取り扱いや第三者への漏洩リスクについて明確にしておく必要があります。
依頼主としては、どちらの場合も「誰が情報にアクセスするか」「利用範囲はどこまでか」を事前に取り決めることで、安心してキャラクターデザイン制作を進めることができます。
【外部依頼】キャラクターデザインの著作権の取り扱いとは
キャラクターデザインを外部に依頼する際、著作権の扱いは依頼主にとって非常に重要なポイントです。依頼主が、広告、プロモーション動画、店頭POP、ゲームなどにキャラクターデザインを使用するためには、著作権の譲渡や利用範囲の確認が欠かせません。
ここでは、制作会社やフリーランスにキャラクターデザインを依頼する際に、必ず押さえておきたい著作権の概要や取り扱いについて解説します。
著作権・著作者人格権の基本情報
まずは著作権・著作者人格権の基本的な概要について押さえておきましょう。
- 著作権
デザインを創作した時点で発生する財産的な利益を保護する権利です。著作権を保有すると、二次利用や複製、改変、商用利用などの権利を行使できます。
譲渡・相続が可能であるため、依頼主が広告やゲームなどでキャラデザインを自由に使用するには、契約で権利譲渡や使用許諾を明示しておく必要があります。
- 著作者人格権
デザイナーが自身の作品に対してもつ人格的な利益を保護する権利です。作品の改変や著作者名を表示した発表、公表の時期・方法などを決める行為を行使できます。
この権利は譲渡・相続はできないため、代わりに契約書にて著作者人格権を行使しないことを約束する「著作者人格権の不行使条項」を設ける必要があります。
制作会社・フリーランスにおける著作権の取り扱いの違い
制作会社やフリーランスにキャラクターデザインを依頼する際、著作権の取り扱いについての違いはあるのでしょうか。ここでは、一般的なケースにおける特徴について解説します。
- 制作会社の場合
制作会社では、会社が契約上で著作権の譲渡や使用範囲をまとめて管理していることが多いため、依頼主は契約書に基づいて使用することが求められます。
譲渡費用は制作費に含まれる場合もありますが、追加で権利を買い取る形になることもあるため、契約時に確認しておく必要があります。
- フリーランスの場合
フリーランスは個人が著作権を保持するケースが多く、依頼主が使用範囲や権利譲渡を希望する場合は契約で明示する必要があります。
権利譲渡や追加利用に伴う費用は、制作料とは別に発生することが一般的です。契約書で「商用利用の範囲」「改変や二次利用の可否」をしっかり取り決めることが重要です。
依頼主としては、契約時に使用範囲、改変可否、商用利用、二次利用、期間などを明確に取り決めることで、追加費用の発生やトラブルを未然に防ぐことができます。制作会社とフリーランスのどちらに依頼するかに関わらず、著作権の取り扱いは事前に十分確認しておくことが重要です。
【関連記事】:企業の大事な公式キャラクターを守る!商標登録の全てを解説
こちらも気になるQ&Aコーナー
ここでは、「キャラクターデザインを外部デザイナー・イラストレーターに依頼する際の費用」について、よくある質問と回答をQ&A形式でまとめています。
Q:キャラクターデザインのロイヤリティの相場は?
A:キャラクターを商品や広告で継続的に利用する場合、使用料(ロイヤリティ)が発生することがあります。利用用途・利用期限・知名度などの要素によって変動しますが、一般的にキャラクターデザインのロイヤリティの相場は「売上の5〜15%程度」といわれています。
Q:キャラデザの三面図の相場は?
A:三面図(正面・側面・背面など)の制作にかかる相場は、一般的に2万~10万円程度といわれています。通常の立ち絵より工数がかかるため、デザインの精密さに比例して費用が高額になる傾向があります。
Q:アニメのキャラクターデザインの相場は?
A:アニメ制作用のキャラクターデザインの費用相場は、1体あたり3万円〜30万円程度が目安です。設定画や複数の表情差分などが必要となるため、場合によっては高額になる可能性もあります。
Q:キャラクターの著作権はいくらかかりますか?
A:著作権譲渡にかかる費用は公開されていないことが一般的です。制作会社の場合には、基本的に個別案件ごとに相談する必要があります。フリーランスの場合、イラスト料金の2倍〜3倍程度が目安です。
ただし、著作権譲渡が不可の場合も多くあるため、事前に確認することが重要です。
Q:キャラクターの立ち絵の相場はいくらですか?
A:キャラクターの立ち絵の相場は、数千円〜3万円程度です。ポーズや衣装差分を追加する場合は、その都度追加費用がかかります。
Q:VTuberのキャラクターデザインの相場はいくらですか?A:VTuber用キャラクターデザインの費用相場は、5万円〜100万円程度です。Live2Dや3Dモデル化を前提にするため、表情・パーツ分けが必要になるため、高額になりやすい傾向にあります。人気デザイナーに依頼する場合、さらに高額になることもあります。
【関連記事】:依頼方法やサービスの利用シーン別におすすめのイラスト依頼方法と相場を解説!
【まとめ】結局どちらが得?制作会社とフリーランスのキャラクターデザインに関する費用相場

キャラクターデザインを外部に依頼する際、単に制作費だけで判断すると「フリーランスは安価」「制作会社は高額」と考えられるかもしれません。しかし、実際には制作費以外にも、権利関係の取り扱いやトラブル時のリスク対応など、見えにくいコストも検討する必要があります。
制作会社とフリーランスのキャラクターデザインに関する費用とリスクを、以下にまとめました。
| 項目 | フリーランス | 制作会社 |
| 制作費の相場 | キャラクターデザインは、相場が数千円~〜5万円程度と安価 | 10万円以上になるケースが多い |
| 著作権・権利の扱い | 権利について、明確に契約書面に起こす必要がある | 契約で利用範囲が明確化されていることが多い |
| リスクと見えないコスト | 納期遅延・音信不通のリスクあり | トラブル時のサポート体制が整っており、余計なコストが発生しにくい |
| 時間・対応力 | 小回りが利き柔軟な対応が可能 | スピードは劣る場合もあるが、大規模案件や長期案件に強い |
結局どちらを選ぶべきか?安心かつ安価な依頼を実現する「cone」の活用がおすすめ
ここまで、制作会社とフリーランスにキャラクターデザインを依頼した場合の違いについて解説してきました。すべてをまとめると、「安さ・スピーディーさ」を重視するならフリーランス、「品質・安心感」を重視するなら制作会社という選択肢になります。
ただし、多くの依頼主にとって最も重要なのは「コスト」「品質」「スピーディーさ」「安心感」のバランスです。
そんな希望をもつ法人企業や個人事業主におすすめなのがクリエイティブ分野に特化したクラウドソーシングサービス「 cone」です。
企業案件に特化したプラットフォームで、契約まわりの手続きやセキュリティも安心して、キャラクターデザインを依頼できます。
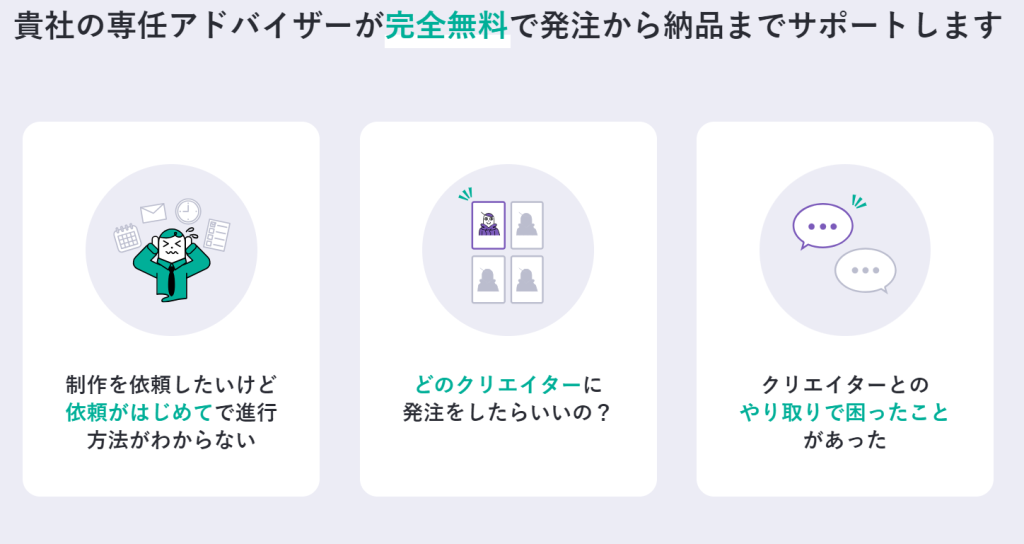
coneには、様々なニーズに対応できる実績豊富なプロのクリエイターが多数在籍しています。
ご希望の予算や納期に応じたご提案も可能です。
イラスト依頼のサポートや相談、「cone」の詳細をご希望の場合は、お気軽に「お問い合わせ」ください。