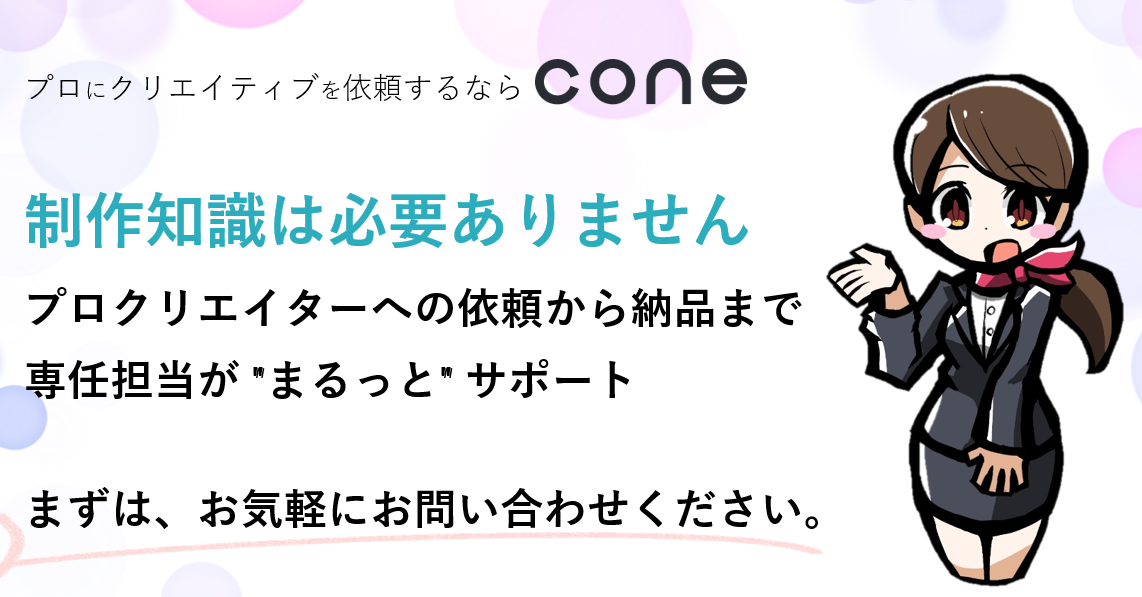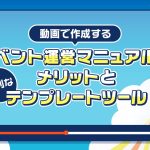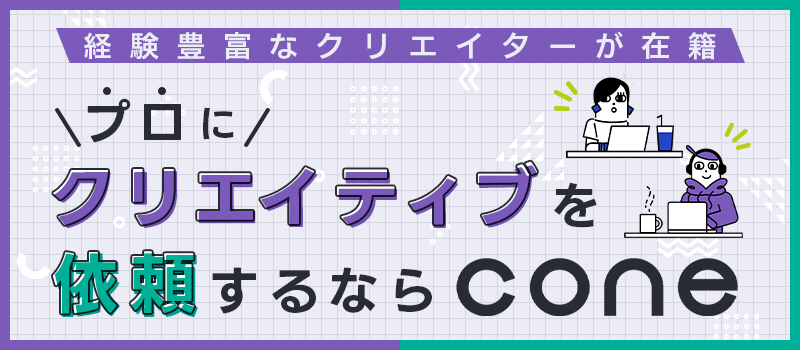企業活動において公式キャラクターは、単なるデザインにとどまらず、商品やサービスを象徴する「顔」として機能しており、ブランド戦略の中核を担う知的財産ともなりえます。
しかし、キャラクターを活用した商品展開や広告宣伝が主流になってきた一方、不正使用や第三者による模倣といった権利侵害のリスクも高まっています。その際、公式キャラクターを、適切に保護するための手段が「商標登録」です。
そこで、本記事では公式キャラクターの保護手段として有効な「商標登録」について、制度の概要や仕組み、登録手続きの流れをわかりやすく解説します。
目次
商標登録とは
商標登録とは、企業や個人が商品名・サービス名・ロゴ・キャラクターなどを特許庁に登録し、独占的に使用できるようにする制度です。ブランドを保護し、市場における信用を守るための重要な手続きです。
商標登録の主な機能
以下の3つが商標登録の基本的な役割です。
- 出所表示機能
どの企業・個人が提供している商品・サービスであるかを消費者に明確に伝える役割があります。 - 独占排他権の付与
登録された商標は、同一・類似の商標を他者が無断で使用することを防ぎます。これにより模倣や不正利用を防止できます。 - 消費者保護機能
信頼できるブランドが偽造されることを防ぎ、消費者が誤って他社の商品・サービスを選んでしまうリスクを軽減します。
公式キャラクターは商標登録すべき?得られる権利とは

企業や団体にとって、公式キャラクターは単なるマスコットではなく、商品やサービスの認知度やブランド価値を高めるための重要な知的財産です。消費者がキャラクターを見て企業や製品を連想し、愛着をもつようになると、そのキャラクターは「ブランドの象徴」として強い影響力を持ちます。
しかし、キャラクターが広く認知されるほど、第三者による模倣や無断使用のリスクも高まります。こうしたリスクに対抗するためには、商標登録による法的保護が不可欠です。
例えば、商標登録によって以下のような効果が得られます。
- 第三者による類似キャラクターの使用を防止できる
- 不正利用に対して差止請求や損害賠償請求が可能になる
- 公式なライセンスビジネス展開が容易になる
このように、公式キャラクターを商標登録することで、ブランド戦略を支える公式キャラクターの役割を十分に果たすことになるとともに、法的トラブルから会社自体を守る予防策にもなるため、商標登録は重要なのです。
ここでは、商標登録によって守られる主な権利や得られる権利を具体的に解説します。また、商標登録では守られない注意すべき部分についても紹介します。
商標登録で守られる主な権利
以下に、公式キャラクターを商標登録する際に守られる主な権利区分とその内容についてまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文字商標 | キャラクター名など、文字で表される名称を保護。 |
| 図形商標 | キャラクターのビジュアル(図形・ロゴ)を保護。 |
| 結合商標 | 名称と図形を組み合わせた全体のデザインを保護。 |
| 役務・商品範囲 | 使用対象となるサービスや製品のカテゴリを明確化。 |
登録によって得られる主な権利
商標登録を行うことで、法的な根拠を持って他者の使用を制限したり、商業展開を優位に進めたりすることが可能になります。以下に、商標登録によって得られる代表的な権利をまとめました。
- 独占的利用権
登録されたキャラクターは、登録者(企業や個人)が指定した商品・サービスの範囲内で独占的に使用できます。他者が同じ名称やビジュアルを使用することは原則として禁止されます。 - 差止請求権
他人が登録キャラクターを無断で使用している場合、使用中止を求める「差止請求」を法的に行うことができます。これにより、模倣品の流通やブランド毀損のリスクを抑えることが可能です。 - 損害賠償請求権
不正な使用によって自社に損害が生じた場合、その損害分の賠償を請求できます。 - ライセンス許諾権
自社での利用にとどまらず、第三者(企業、メディアなど)にキャラクターの使用を許諾することが可能です。ライセンス契約を通じて収益化しやすくなる点も事業戦略の一環として活用できます。
こうした権利は、単なる「イメージ保護」にとどまらず、公式キャラクターをビジネスに活用するうえで欠かせない法的基盤となります。特に、コラボレーション商品や広告起用、ライセンス展開を検討している場合には、商標登録は不可欠です。
商標登録の範囲外となるケース
商標登録は、キャラクターの名称や図形といった「識別標識」を保護する制度です。そのため、キャラクターのあらゆる要素が自動的に法的に守られるわけではありません。
以下のような側面については、商標法の保護範囲外となるため、別途の対応が必要です。
- 商品・サービスの識別標識として使用していない場合
商標登録ができるケースは、あくまで商品・サービスを識別するマークやシンボルとして機能している場合に限られます。そのため、まったく無関係の商品・サービスとキャラクターを結びつけた商標登録は難しいでしょう。 - 登録範囲外での利用(未登録カテゴリでの使用)
商標は「指定商品・役務」に限定して効力が発生します。例えば、お菓子カテゴリで商標登録しても、アパレルや文具など別カテゴリでの模倣は直接防げません。
商標登録はキャラクターの一部を守る有効な手段ではありますが、キャラクターを網羅的に保護できるものではない点に注意することが大切です。他の知的財産権や契約との併用が、トラブル回避につながります。
公式キャラクターにおける商標登録と著作権の違い
公式キャラクターに関する知的財産権には、商標権だけでなく「著作権」や「著作者人格権」も関係します。これらの違いを理解しておくことは、キャラクターを安心して活用・運用していくうえで重要です。
ここでは、公式キャラクターにおける商標登録と著作権の違い、著作者人格権、よくあるトラブルについて解説します。
商標登録と著作権の主な違い
以下に、商標登録と著作権の主な違いをまとめました。
| 項目 | 商標登録 | 著作権 |
|---|---|---|
| 保護対象 | 商品・サービスを識別するキャラクターの名前・ロゴ・図形など | キャラクターのビジュアルや設定、表現など |
| 取得方法 | 特許庁への登録が必要 | 創作と同時に自動的に発生 |
| 保護の目的 | 出所の明確化や商品・サービスの独占利用 | 創作者の権利や作品の無断利用防止 |
| 登録期間 | 原則10年(更新可能) | 著作者の死後70年まで |
| 管轄 | 特許庁 | 文化庁(登録不要) |
著作者人格権とは
著作権と併せて重要なのが「著作者人格権」です。これは、著作物が創作者の人格的表現であることから、以下のような権利が認められています。
- 氏名表示権:著作者名を表示するかどうか、また表示方法を決定する権利
- 同一性保持権:著作者の意に反して、無断で改変されることを拒否する権利(色やデザインの変更なども対象)
- 公表権:作品をいつ・どこで公開するかを著作者自身が決める権利
これらは譲渡や放棄ができない「一身専属の権利」であることから、注意して対応する必要があります。
著作権に関するよくあるトラブル
公式キャラクターを外部のクリエイターに依頼して制作した場合、以下のような認識のズレからトラブルにつながることがあります。
- 発注者側の主張:「費用を払ったのだから、すべての権利は自分にあるはず」
- 制作者側の主張:「著作権は自動的に私にあるので、自由に使うには許可が必要
このようなトラブルを防ぐためには、契約書で著作権・著作者人格権の取扱いを明確にしておくことが重要です。場合によっては、著作権の譲渡や使用許諾の範囲まで定めておくことが求められます。
【関連記事】:イラストの仕事にかかわる権利とは?イラストを依頼する際の注意点
商標登録における法人・個人の違いと注意点
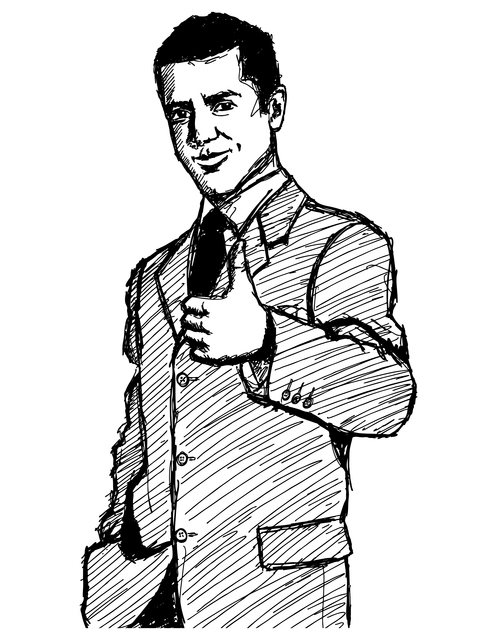
商標登録は、法人・個人のどちらも申請可能ですが、登録後の運用やリスクは異なります。それぞれの特性と注意点を理解しておくことが、適切な権利管理につながります。
ここでは、商標登録における法人・個人の違いや注意点について解説します。
法人・個人における商標登録の主な違い
以下に、商標登録における法人・個人の主な違いをまとめました。
| 項目 | 法人の場合 | 個人の場合 |
|---|---|---|
| 登録名義 | 会社名義で登録され、資産として管理可能 | 個人の名前で登録し、本人が直接権利を保有 |
| 個人情報の公開の可能性 | 個人情報の公開を回避できる | 個人の住所が公開される可能性がある |
| 敵対的買収時 | 法人とともに商標権も移転する | 買収による商標権の移転はない |
| 活用の継続性 | 組織運営により継続的な使用がしやすい | 活動が停止すると使用実績が途絶えるおそれがある |
| 承継・譲渡 | 組織内での承継・譲渡が比較的容易 | 相続や譲渡には手続きが必要 |
注意点1:不使用取消審判のリスク
商標登録後、3年間正当な使用がなければ「不使用取消審判」を申し立てられるリスクがあります。特に個人の場合、実際のビジネス活動と乖離したまま登録していると、使用実績の証明が困難となり、取消されるおそれがあります。
そのため、登録後の運用においては「登録後は継続的な使用実績を残す」「名義と実態を一致させる」といった対策が必要です。
注意点2:財産管理と承継
商標権は「財産権」として扱われるため、適切な管理・承継体制が必要です。
- 法人名義の場合:代表交代や事業承継があっても、法人が継続すれば問題なし
- 個人名義の場合:死亡・引退時に相続人への承継手続きが必要となり、手続きに時間がかかるケースがある
このように、法人・個人で大きく管理・承継が異なるため、個人で登録する場合には、早めに手続きを行うことが求められます。
商標登録の方法
商標登録は、特許庁への正式な出願を経て審査を受けることで成立します。以下の項目に沿って準備・手続きすることで、スムーズに登録まで進行できます。
1.事前調査
商標の使用可否を判断するため、事前に既存の登録商標と類似していないか調査を行います。
例えば、「類似するキャラクターやロゴがすでに登録されていないか」「指定する商品・サービス分類(区分)はどれか」などを確認しましょう。
その際、不安があれば弁理士などの専門家に、調査代行を依頼することもおすすめです。より確実な調査につながります。
2. 申請準備
調査により、商標登録を行うことが確定したら、申請に必要な書類を整えます。以下に申請場所や必要書類、提出方法をまとめましたので、参考にしてください。
| 申請機関 | 特許庁 |
|---|---|
| 必要書類・情報 | 商標の名称・図形、出願人情報、使用予定の商品・サービス |
| 出願料 | 3,400円+(区分数×8,600円)電子化手数料(紙の書類による手続きの場合):2,400円+枚数×800円 |
| 提出方法 | オンライン(電子出願ソフト)紙の書類の郵送紙の書類を窓口に提出 |
| 出願人の種類 | 法人または個人(代理人による申請も可能) |
3. 審査の実施
申請書類をもとに、約6か月〜1年という長期間にわたって特許庁による審査が行われます。審査は、以下の2つに区分されています。
- 方式審査:書類や形式に不備がないかの確認
- 実体審査:法的な登録要件(識別力・類似性等)を満たしているかを精査
審査した結果、申請内容に問題がなければ「登録査定」が通知されます。
4. 拒絶理由通知への対応
審査の結果、登録に支障があると判断された場合、「拒絶理由通知」が届きます。その場合、以下の対応が求められます。
- 意見書の提出:審査官の指摘に対して法的根拠をもとに反論
- 補正書の提出:商標内容や指定商品・役務の修正など
ただし、原則として通知から40日以内に対応しなければならず、専門的な内容になるケースが多いため、弁理士にサポートを依頼することがおすすめです。
5. 登録査定の発行
審査において拒絶理由が解消され、商標として登録に適していると判断されると、「登録査定」が発行されます。
登録査定とは、審査を通過した証として、特許庁から送付される決定通知のことです。登録査定が発行されたら、「出願商標が商標法上の要件を満たした」と認められたことを示します。
6. 登録料の納付(登録査定から30日以内)
登録を確定させるには、登録査定の発送日から30日以内に、以下の登録料を支払う必要があります。
| 費用項目 | 金額(1区分あたり) | 支払い方法 |
|---|---|---|
| 登録料(5年分) | 区分数×17,200円(分割) | 現金、クレジットカード、口座振替、電子現金納付、印紙、予納など |
| 登録料(10年分) | 区分数×32,900円 |
7.設定登録が済み、登録証が交付される
納付完了後、登録証が交付されます。商標登録が正式に発生するのは、この段階になってからです。商標登録は、一度登録すると10年にわたり継続して効力が発生します。
【関連記事】:VTuberの著作権譲渡とは?相場とトラブル回避のポイントを解説
クリエイターの選定から依頼のやりとりを専任担当がサポート!
「自分でイラスト依頼のやりとりをするのが不安…」という方は、ぜひ「cone(コーン)」をご活用ください。
実際に、クリエイターの選定を行うのもなかなか大変… 「すぐに返信が来るかわからない…」「権利周りの相談で時間が掛かりそう…」など、商用利用では特にクリエイターへ依頼するまでに時間が掛かる事が多く、慣れていないと大変なんです…
そんな時は!
coneは法人企業からクリエイターへ依頼ができるサービス。
専任スタッフがクリエイターとのやりとりを代行し、納品までサポートします!
まずは、お気軽にご相談、お問い合わせください。
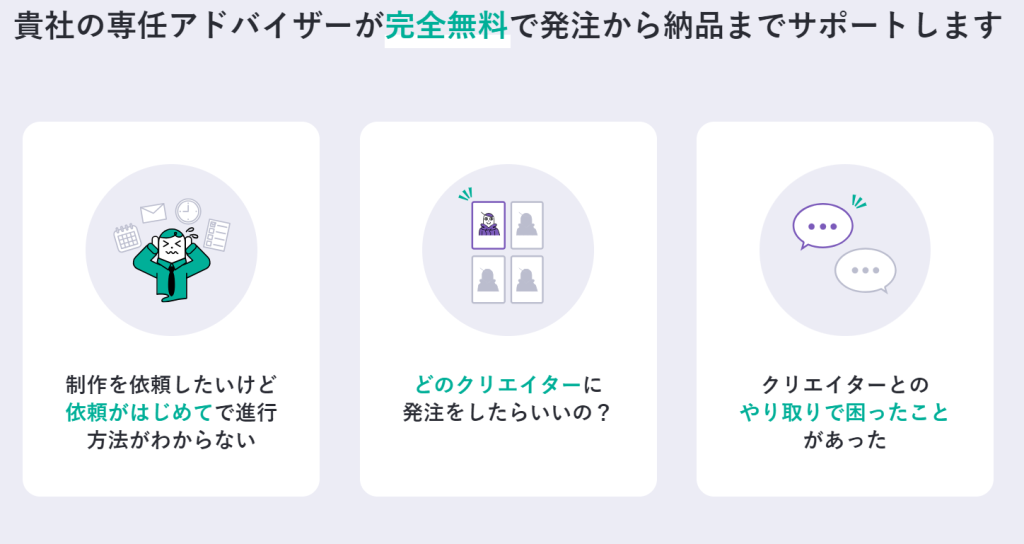
coneには、様々なニーズに対応できる実績豊富なプロのクリエイターが多数在籍しています。
ご希望の予算や納期に応じたご提案も可能です。
イラスト依頼のサポートや相談、「cone」の詳細をご希望の場合は、お気軽に「お問い合わせ」ください。