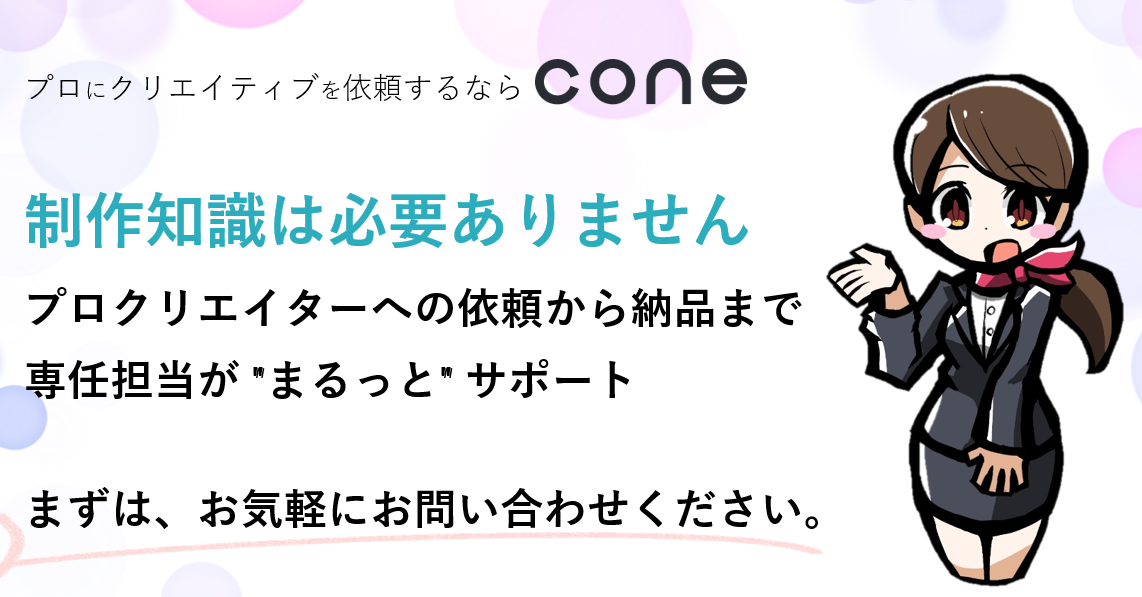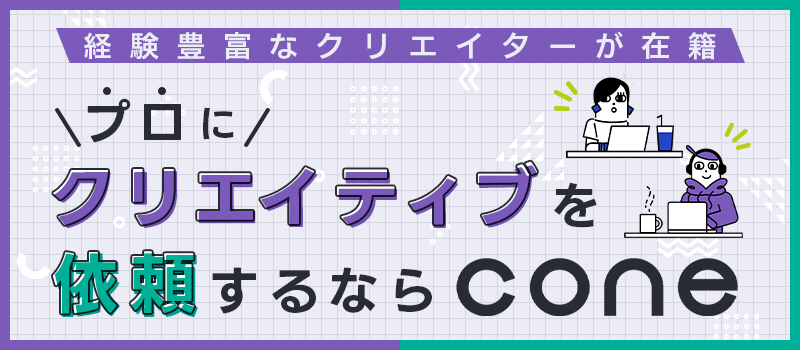業務マニュアルといえば、かつては紙媒体やPDFの文書が主流でした。
しかし最近では、より直感的にかつ効率的に学習できる「動画マニュアル」が注目を集めています。特に社内教育や製品・サービスの操作説明など、幅広いシーンで導入が進んでおり、「動画で覚える」学習スタイルが定着しつつあります。
そこで、本記事では動画マニュアルを導入するメリットから、実際の作り方、活用に適した業務内容、便利な作成ツール、さらに分かりやすい動画を作るコツまで、ステップごとにわかりやすく解説します。
目次
動画マニュアルを作るメリット
動画マニュアルは、文章で作成されたマニュアルと比べて複雑な内容でも理解しやすい「資産」として、あらゆる業種・規模の企業で活用されています。ここでは、動画マニュアルのメリットを解説します。
- 直感的に理解できる
- 動画マニュアルは、視覚と聴覚の両方から情報を伝えられるため、テキストだけでは理解しにくい手順や作業の流れも、直感的に把握できます。
また実際の操作や動作を見せることで、言葉に頼らずに内容が伝わることから、言語の壁がある外国人スタッフや知識や経験が浅い新入社員にも有効です。 - 具体的な説明を短時間で伝えられる
- テキストマニュアルでは、各動作を詳細に説明する必要があるため、作業全体を記載すると内容が冗長になりがちです。
動画マニュアルであれば、短時間で簡潔に情報を伝えることができます。
例えば「このボタンを押してから2秒待って次の操作に進む」といったタイミングも、動画なら一目瞭然です。 - 教育コストを削減できる
- 動画マニュアルは一度作成すれば、何度でも繰り返し使用可能です。新入社員が入社するタイミングがズレた場合にも、講師や先輩社員による都度の指導が不要になり、教育にかかる時間や人件費を大幅に削減できます。
また動画の制作データも保存しておくことで、マニュアルの一部に変更があった際もその部分だけを撮影し、編集することで簡単に更新できます。 - 繰り返しの学習が可能
- 学習者は自分のペースで繰り返し視聴でき、わからない部分を巻き戻して確認することも容易です。
また動画マニュアルをサーバーやクラウド上で保存することで、社員はアクセス権がある社内のパソコンやタブレット、スマートフォンなどのデバイスで、場所や時間を問わずいつでも閲覧できるようになります。
セキュリティ対策は必須ではあるものの、自己学習が可能となり、理解度が向上し、実務への定着もスムーズになります。
動画化に向いているマニュアル
すべてのマニュアルが動画に適しているわけではなく、「動き」や「手順」が重要となる作業内容は、動画化の効果が大きいです。ここでは、動画化に向いているマニュアルの例を解説します。
- 業務の手順書
- 業務フローや具体的な手順は、文字や写真だけでは伝えづらいものです。
業務の工程や順序、進め方をまとめた業務手順書を動画にすることで、業務全体の流れが把握しやすくなり、実際の業務進行をよりスムーズに行うことができます。
動画マニュアルでは「実際に作業しているところを見せる」ことで、流れを視覚的に理解でき、実務への定着を促進します。 - 営業や接客のマニュアル
- 営業や接客などの対人での振る舞いや話し方、表情、動作などは、テキストでは表現しきれない重要な要素です。そのため、営業職・販売職向けのマナーやノウハウは、視覚的に理解しやすい動画マニュアルに向いています。
ロールプレイ形式の動画マニュアルを作成し、実際の対応例を見せることで、視聴者は「どのように振る舞えばよいか」をイメージしやすくなります。 - 機械やツールの操作マニュアル
- 複雑な動作や正確な手順を行う必要のある機械・ツールの操作は、動画にすることで具体的な操作方法と手順を伝達できます。
例えば、「製造ラインの作業手順」「レジの操作方法」などが挙げられます。こうした操作マニュアルを作成する際は、手元の動きを映すことが大切です。誤操作の防止や事故・故障のリスク減少に役立ちます。
【要Check!】関連記事:動画マニュアルが解消する製造業の課題とは?紙マニュアルとの違いと作成の流れも解説
動画マニュアルの作り方をステップで解説
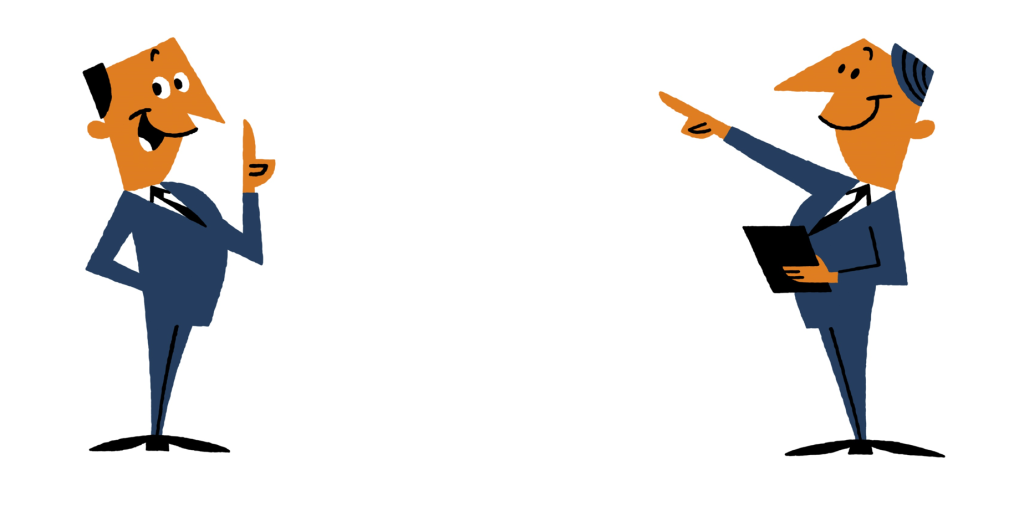
動画マニュアルの作成には、単に動画を撮影するだけでなく、「目的の明確化~編集」までの一連の流れを踏むことが重要です。ここでは、誰にとってもわかりやすく効果的な動画マニュアルを作成するためのステップを5つに分けて解説します。
- 1.目的を明確にする
- まず行うことは、動画マニュアルを「何のために作るのか」「誰に見せたいのか」という目的と対象を明確化することです。目的が明確になることで、伝えるべき情報や表現のトーン、構成などが定まり、より効果的な動画作りにつながります。
そのため、目的が明確かつ具体的であればあるほど、動画マニュアルのクオリティや粒度が見えてきます。 例えば、「新卒向けの新人教育のOJTのうち、6割を動画マニュアルでまかなえる内容にする」という目標の場合には、前提となる基本情報や作業内容の細かな部分まで動画マニュアルに組み込むべきと判断できるでしょう。 - 2.情報を収集・整理する
- 目的が定まったら、動画に含めるべき情報の収集と整理を行います。
作業手順や使用ツール、注意点、操作のコツなど、対象者が知っておくべき内容を漏れなく洗い出すことが重要です。この段階で実際の作業担当者にヒアリングを行ったり、既存のマニュアル資料を活用することで、現場に即したリアルな内容を盛り込むことができます。
特に「どこでミスしやすいか」「初心者がつまずきやすい点はどこか」といった情報は、動画マニュアルの質を左右するポイントになります。 - 3.構成・台本を作成する
- 収集した情報をもとに、動画マニュアルの構成・台本を設計します。
一般的な動画マニュアルの構成は、「全体の目的やゴールを簡潔に伝える→各工程の順を追って解説する」という流れが基本です。作業単位でチャプターを分けたり、重要な場面で区切りを設けると、対象者にとってわかりやすい動画マニュアルになるでしょう。
また、この段階で台本も作成しておきます。 台本には、構成に沿って使用する資料映像やナレーションの原稿、テロップの内容も盛り込みます。台本を作成してから撮影を始めることで、素材不足や撮り方のミスを防ぎ、スムーズな進行につながります。 - 4.動画を撮影する
- 構成に基づいて、実際の撮影に入ります。
作業風景やツールの操作などを撮影する場合は、手元がしっかり映るカメラ位置の確保や、作業環境の整理が重要です。
また、ナレーションを入れる際には、雑音の少ない場所で録音し、クリアな音声を確保しましょう。必要に応じて画面録画ソフトを使用し、パソコンの操作画面を記録するのも効果的です。
一発で完璧に撮影する必要はありません。編集によって一本の動画に仕上げることを前提とし、一つひとつの素材を丁寧に撮影・録音しましょう。 - 5.動画を編集する
- 撮影が完了したら、素材をつなぎ合わせて編集作業を行います。
不要な部分をカットしたり、手順の間にテロップや説明文を挿入したりすることで、視聴者がより理解しやすい内容に仕上げます。
また、注意点や重要な操作は、ズームや色変え、音声の強調などの演出でメリハリをつけると効果的です。視聴時間はできるだけコンパクトにし、必要な情報が不足なく伝わるように心がけましょう。
無料・有料のおすすめツールを紹介
動画マニュアルの作成には、単に動画を撮影するだけでなく、「目的の明確化~編集」までの一連の流れを踏むことが重要です。ここでは、誰にとってもわかりやすく効果的な動画マニュアルを作成するためのステップを5つに分けて解説します。
動画マニュアルを作成する際には、目的や予算、社内の制作体制に応じて、適切なツールを選定することが重要です。
ツールには高機能で多機能な有料ツールと、導入コストを抑えながら手軽に利用できる無料ツールがあり、それぞれに特徴とメリットがあります。
ここでは、代表的なツールについて概要や特徴、費用感を交えてご紹介します。
有料ツール
ここでは、代表的な有料ツールを3つ紹介します。
- カミナシ教育
- 現場向けの教育コンテンツを動画で作成・配信・管理できるクラウドサービスです。
現場作業の流れに沿って直感的なUIでマニュアルを作成でき、受講者ごとの習熟度の進捗管理機能やAI自動字幕・音声翻訳機能も搭載されています。
料金は「初期費用+月額料金」で、月額料金は料金プランやID数によって変動します(要問い合わせ)。 - tebiki
- スマホで簡単に撮影・編集・字幕付けができる動画マニュアル作成ツールです。
業務改善を計画的に整備できる「作成計画表」やノウハウごとの動画マニュアルを1つにまとめる「コース機能」を搭載しており、現場教育全般の改善にも活用できます。
料金プランは、使用できる機能数によって異なり、エントリープラン・ビジネスプラン・エンタープライズプランが用意されています(要問い合わせ)。 - VideoStep
- 「シンプルな操作感」を徹底的に追求し、パワーポイントやエクセルのような使用感で動画作成が可能な動画作成プラットフォームです。
動画マニュアル作成に特化した機能性に絞り込み、シンプルでわかりやすいUIを実現しています。バージョン管理機能、AI動画編集などが搭載されています。
料金は「初期費用+月額料金」制です。月額料金は、使用できる機能数によって異なり、スタートプラン・ビジネスプラン・プロフェッショナルプランが用意されています(要問い合わせ)。
無料ツール
ここでは、代表的な無料ツールを4つ紹介します。
- PowerPoint/Googleスライド
- スライドにナレーションを加えたり、動画としてエクスポートしたりすることが可能です。操作に慣れているユーザーが多いため、導入・作成のハードルが低いのが特徴です。
- Microsoft Clipchamp
- Windows 10以降に標準搭載されているシンプルな動画編集ソフトです。 基本的なカット編集やテキスト追加、音楽挿入といった機能がそろっており、初心者でもすぐに扱えます。
- iMovie(Mac専用)
- MacやiPhoneなどで利用できるApple製の無料動画編集ソフトです。 用意されているテンプレートを活用することで、手軽に高品質な動画を作成できます。インターフェースも直感的で、編集作業の敷居が低いのが特徴です。
わかりやすい動画マニュアルを作るコツ

わかりやすい動画マニュアルを作成するコツとして、ここでは「作業ごとに動画を作成する」「テロップを入れる」「重要なポイントを強調する」「失敗例を入れる」の4つを解説します。
- 作業ごとに動画を作成する
- 1本の動画に多くの情報を詰め込みすぎると、視聴者が途中で混乱したり、必要な部分を探すのに時間がかかったりしてしまいます。そのため、作業単位や工程ごとに動画を分けて制作するのがおすすめです。
例えば「ログインの仕方」「システムの初期設定」「データの登録方法」など、項目ごとに区切ることで、目的の情報にすぐアクセスできるだけでなく、更新や差し替えも容易になります。
また管理・更新の利便性においても、業務ごとに区切り、それぞれの作業ごとに短い動画を作成することがおすすめです。 - テロップを入れる
- 映像と音声だけでは、環境によって内容が聞き取れなかったり、理解が追いつかないケースがあります。
そこで重要なのが、テロップ(字幕)の活用です。操作手順や重要な説明を文字で補足することで、視覚と聴覚の両方から情報を伝えられ、理解が格段に深まります。
特に初心者や日本語に不慣れな外国人スタッフにとっては、テロップがあることで情報の受け取りやすさが大きく向上します。 - ポイントを強調する
- 注意事項や作業上のコツなどの重要なポイントは、動画内でしっかりと強調する必要があります。具体的には、「テロップの色を変える」「強調したい場面にズームを使う」「効果音を入れる」などの工夫が効果的です。
対象者が「この部分は特に重要だ」と認識することで印象に残り、実務でのミスを防ぎやすくなります。 - 失敗例を入れる
- 正しい操作だけでなく、やってはいけないミスや典型的な失敗例もあわせて紹介することで、より実践的な学びにつながります。
失敗例を示すことで、「こうすると間違える」「こうすれば回避できる」といった具体的な対処方法がわかりやすくなり、視聴者の記憶にも残りやすくなります。
特に業務に不慣れな新入社員や外国人労働者などに対して、非常に有効な手法です。
クリエイターの選定から依頼のやりとりを専任担当がサポート!
「自分でイラスト依頼のやりとりをするのが不安…」という方は、ぜひ「cone(コーン)」をご活用ください。
実際に、クリエイターの選定を行うのもなかなか大変… 「すぐに返信が来るかわからない…」「権利周りの相談で時間が掛かりそう…」など、商用利用では特にクリエイターへ依頼するまでに時間が掛かる事が多く、慣れていないと大変なんです…
そんな時は!
coneは法人企業からクリエイターへ依頼ができるサービス。
専任スタッフがクリエイターとのやりとりを代行し、納品までサポートします!
まずは、お気軽にご相談、お問い合わせください。
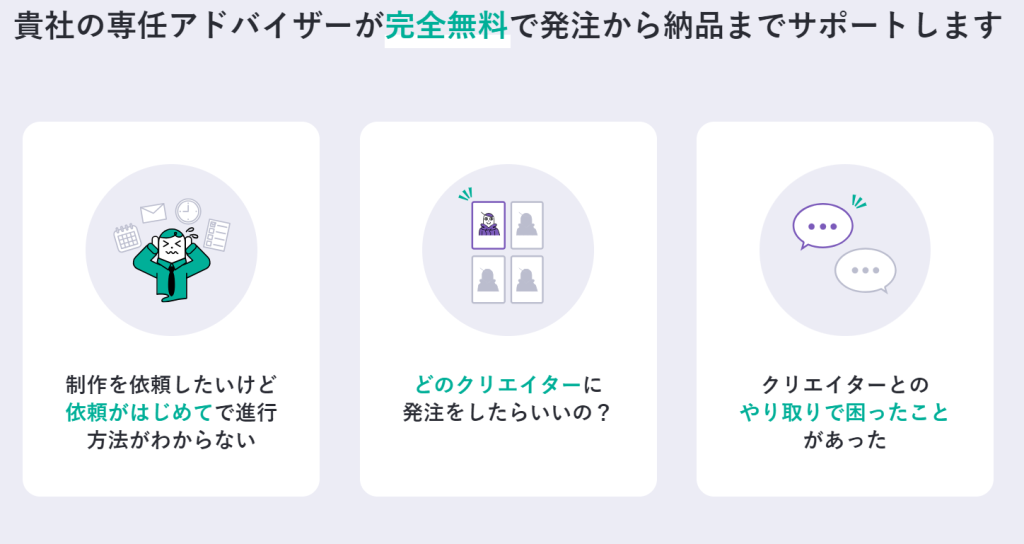
coneには、様々なニーズに対応できる実績豊富なプロのクリエイターが多数在籍しています。
ご希望の予算や納期に応じたご提案も可能です。
イラスト依頼のサポートや相談、「cone」の詳細をご希望の場合は、お気軽に「お問い合わせ」ください。