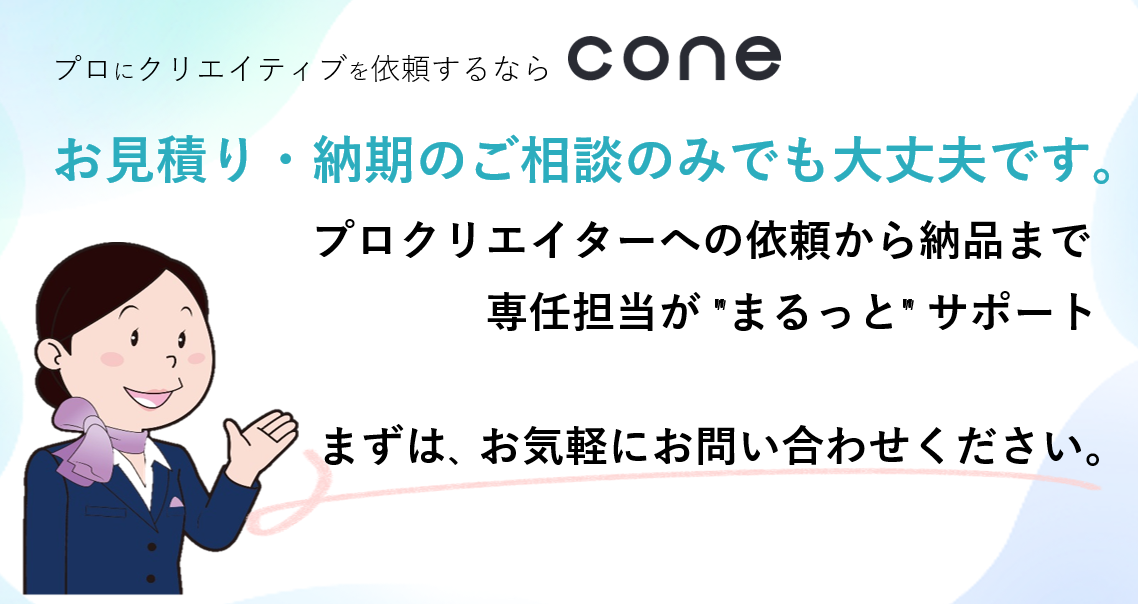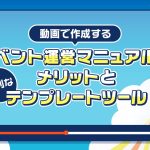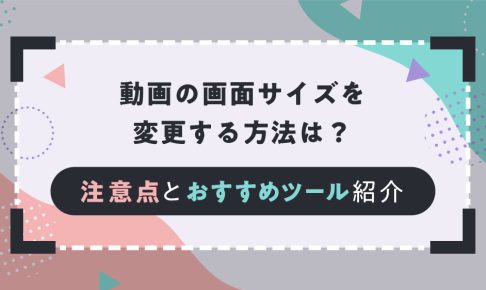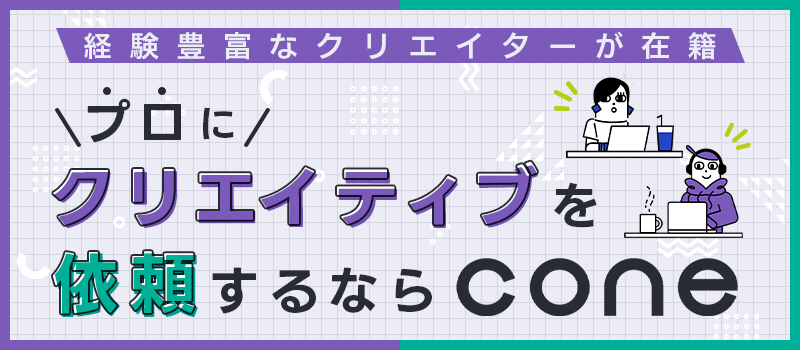業務の標準化や新人教育の効率化を図るうえで、動画マニュアルは非常に有効な手段です。そのため、最近では企業規模や業種を問わず、多くの企業が導入を進めています。
しかし、実際に動画マニュアルを作成しようとすると、「外注すべきか、それとも社内で内製するべきか」といった悩みに直面することが少なくありません。外注・内製のどちらにもメリット・デメリットがあるため、自社に合った方法を選択することが重要です。
そこで、本記事では、動画マニュアルを外注する場合と自社で内製する場合のメリット・デメリット、作成手順を詳しく解説するとともに、成功するためのポイントについても紹介します。
目次
動画マニュアルの作成方法
動画マニュアルを作成する方法は、大きく分けて「外部への依頼(外注)」と「自社内での作成(内製)」の2つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の体制や目的、予算に応じた選択が求められます。
ここでは、動画マニュアルの作成方法として、外注・内製それぞれのメリット・デメリットを解説します。
外注のメリット・デメリット
外注とは、動画制作会社やフリーランスのクリエイターに依頼して、動画マニュアルを制作してもらう方法です。構成作成から撮影、編集、ナレーションや字幕の挿入など、すべてをプロの手で制作されるため、完成度の高い動画が期待できます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 高品質な動画が短期間で納品される撮影・編集の専門スキルが不要ブランディングや視聴者心理を考慮した演出が可能 | コストが高額になりやすい修正や更新に時間・費用がかかる |
内製のメリット・デメリット
内製は、テンプレートツールや簡易編集ソフトを用いて、自社のスタッフが動画を作成する方法です。最近では、スマートフォン1台で撮影から編集、共有まで完結できるツールも増えており、以前より内製のハードルは低くなっています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 費用を抑えられる業務内容や現場事情に即した動画が作れる必要に応じて柔軟に修正・更新が可能 | 撮影・編集スキルが求められるクオリティにばらつきが出やすい作成や更新に時間や人的リソースが必要 |
動画マニュアルを外注する場合の作成手順
ここでは、動画マニュアルを外注する場合の一般的な作成手順を解説します。外注する場合の作成手順を事前に把握することで、スムーズな進行につながります。
1.依頼先を探す
マニュアル動画の制作を依頼できる外注先を探します。
「制作会社」「個人クリエイター」などの選択肢から、業界経験や制作実績、得意ジャンルを確認し、自社に合ったスタイルを持つパートナーを見つけましょう。
制作実績や過去のポートフォリオをチェックすることで、期待するクオリティが得られるか判断できます。
2.問い合わせ・打ち合わせ
複数の候補先が見つかったら、制作の概要を伝えるために問い合わせを行います。
想定している依頼内容や制作目的、尺、希望納期、予算感などを共有しましょう。この時点での情報が明確であるほど、その後の見積もりや提案がスムーズになります。
その後、制作会社と初回の打ち合わせを行い、動画の用途・構成・撮影場所・出演者の有無などの具体的な内容を決定します。既存の業務マニュアルや資料があれば、この段階で共有しておくと、構成の設計がスムーズになります。
3.契約する
打ち合わせ内容をもとに、制作会社や個人クリエイターから正式な見積書や契約書が提示されます。
契約書面には、制作費用や納期、納品形式、修正回数、著作権や使用権の取り扱いといった条件が明記されるため、双方で内容をしっかり確認したうえで締結しましょう。トラブルを防ぐためにも、不明点は事前に確認しておくことが大切です。
4.動画制作
契約締結後、制作会社が構成案を作成し、撮影・編集作業へと進みます。撮影が自社施設で行われる場合は、立ち会いの調整や社員のスケジュール調整が必要です。
編集途中では、確認用のラフ映像が共有されるケースも多くあり、そのタイミングでフィードバックを行います。フィードバックのタイミングや回数に制限がある場合もあるため、必ず自社の希望に沿っているか確認しましょう。
5.納品
最終的な編集が完了した動画は、指定の形式で納品されます。納品後は社内で確認を行い、必要に応じて修正依頼を行います。
修正は契約時の条件に従って対応されるため、修正点をまとめて具体的に伝えるのがポイントです。
動画マニュアルを外注する際のポイント

動画マニュアルを外注する際は、プロに任せる分、「コストパフォーマンスや仕上がりの品質が、自社の期待と合致するかどうか」が成功もしくは失敗を判断する基準になります。
そこで重要となるのが、「予算の設定」と「目的・用途の明確化」です。この2つのポイントを押さえておくことで、無駄な出費や成果物とのズレを回避できます。
予算の上限を決める
外注制作には、構成・撮影・編集・ナレーション・修正対応などの各工程ごとに費用が発生します。そのため、動画マニュアルの種類や依頼する作業範囲によって費用は大きく異なります。
例えば、簡易的な説明動画であれば10万円前後でも作成できますが、構成から演出までフルサポートを依頼する場合は50〜100万円を超えるケースもあります。
そこで重要になるのが、あらかじめ社内で予算の上限を設定しておくことです。
事前に「○○万円以内で収めたい」という基準をもつことで、依頼先との交渉や見積もりの比較がスムーズになります。また、オプションを追加することで費用も増えていくため、オプション費用にも注意が必要です。
動画マニュアル作成にかかる費用については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:動画マニュアルにかかる費用を徹底解説!費用を抑えるポイントも紹介
目的・用途を明確にする
動画マニュアルを制作する際には、「誰に、何を、何のために作るのか」を明確にすることが重要です。
例えば、現場スタッフ向けの機器操作マニュアルなのか、営業職向けのヒアリング研修用動画なのかによって、構成やトーン、演出が大きく異なります。
そのため、目的が曖昧なまま依頼をすると、完成した動画が「想定と異なる」「使いづらい」といった問題につながる可能性があります。これを防ぐには、次のような要素をあらかじめ整理し、外注先と共有しておくことが効果的です。
- 対象者:新入社員、店舗スタッフ、外部パートナーなど
- 伝えたい情報の範囲:接客全体の流れ、レジ操作のみなど
- 使用する場面:入社初日、業務開始前の確認用、研修教材など
- 目的:業務手順の標準化、属人化の防止、顧客対応の品質向上など
このように具体的な背景や活用目的が明確であれば、制作側も意図を汲み取りやすく、結果的に満足度の高い動画に仕上がります。
動画マニュアルを内製する場合の作成手順
動画マニュアルの内製(自社制作)は、コストを抑えつつ、現場に即した内容の動画を柔軟に作成できます。ただし、制作の各工程を自社で担う必要があるため、段取りよく進めるための作成手順の理解が欠かせません。
そこで、ここでは内製の基本的な作成手順を5つのステップに分けて解説します。
1.業務の手順・ルールを整理する
まずは動画にしたい業務や作業手順、ルールを整理します。
対象となる作業の全体像を明確にし、「どの場面を動画化するか」「どこまで細かく説明するか」を決める必要があります。
例えば、以下のような観点で整理すると良いでしょう。
- 作業手順は何ステップあるか
- 動画化の優先度はどの作業が高いか
- どの部分でミスが起こりやすいか
- 音声・映像で表現すべき重要ポイントはどこか
あらかじめ動画化する業務の手順書やチェックリストを作成しておくと、スムーズな動画撮影や編集が可能です。
2.ツールを選定する
動画マニュアルを制作・編集するためのツールを選びます。初心者であれば、テンプレート型の動画作成ツールを活用することで、簡単に作成が進められます。
本記事の後半で、動画作成ツールの選定ポイントについても解説していますので、あわせてご覧ください。
3.構成の作成
動画の内容が決まったら、構成を作成します。
構成とは、どの順番で、どの情報を、どのような映像・ナレーションで伝えるかを整理する作業です。いわゆる「絵コンテ」や「台本」にあたるもので、完成度の高い動画に仕上げるためにはこの工程が非常に重要です。
例えば、「挨拶→目的・概要の説明→手順1→手順2→注意点・ポイント→まとめ」というような流れで構成を立てることが一般的です。
この他にも、以下のような細部まで練り込んでおくことで、撮影や編集もスムーズに進行できます。
- ナレーションの原稿や字幕内容
- 画面表示(テキスト、イラスト、写真、動画の組み合わせ)
4.動画撮影
構成に基づいて、実際の動画を撮影します。
撮影時は、実際の現場や使用環境での撮影を意識しましょう。視聴者がそのまま真似できるように、視界が開けたアングル、作業の流れがわかるカット、重要な動作の手元アップなどを意識して撮影することが大切です。
必要であれば、同じ作業を何度か繰り返し、カット編集しやすい素材を撮っておきます。
5.動画編集
撮影した素材を編集ソフトに取り込み、構成に沿って編集を進めます。
以下のような要素を適切に加えることで、視聴者が動画内容を理解しやすくなります。
- ステップごとのテロップ表示
- 音声ナレーションやBGMの追加
- 重要箇所のズームやハイライト
- 説明イラストや図表の挿入
編集後は、必ず社内でテスト視聴を行い、「実際に業務ができる内容になっているか」「視認性は問題ないか」を確認しましょう。
動画マニュアルを内製する際のポイント

内製で動画マニュアルを作成する場合、制作コストを抑えつつ自社に最適化した内容を作ることができる反面、クオリティの維持や制作効率の確保が課題となります。
そこで、ここでは内製の成功に不可欠な2つのポイントである「適したツールの選定」と「撮影・編集時の工夫」について詳しくご紹介します。
自社に適したツールを選ぶ
動画マニュアルを内製する際、まず直面するのが「どのツールを使うか」という選定です。ツールによって機能や料金、使いやすさ、サポート内容などが大きく異なるため、自社の制作体制や運用目的に適したものを選ぶことが成果を左右します。
例えば、以下のような観点で検討すると良いでしょう。
- 制作担当者のスキルレベル
動画制作担当チームに初心者が多い場合は、操作が簡単なテンプレート型ツールがおすすめです。 - 運用方法
現場でスマホで視聴させたい場合は、QRコード共有やオフライン再生機能があるものが便利です。 - 更新頻度
頻繁に更新する前提であれば、編集や差し替えが簡単なクラウド型ツールが向いています。 - 費用対効果
無料体験版で操作性や機能を確認してから、有料版の導入を検討しましょう。
ツールの選定は、社内における動画マニュアルの定着にも関わるため、使いやすさと継続性を重視して選ぶことが重要です。
関連記事:動画マニュアル作成ソフトのおすすめ5選!選び方も詳しく解説
動画撮影・編集を工夫する
内製の弱点は、「プロに比べてクオリティが劣りやすい」点にあります。
しかし、動画マニュアルは社内のスタッフに「業務内容を伝える」ものであるため、「わかりやすさ」が何よりも重要です。そして、わかりやすさにおいては、撮影・編集時の工夫で向上できます。
以下のようなテクニックを意識して、社内スタッフが理解できる・わかりやすい動画マニュアルづくりを目指しましょう。
| 撮影時にできる工夫 | 編集時にできる工夫 |
|---|---|
| 作業時の手元や重要部分はクローズアップして撮影照明の明るさや背景色を調整する三脚などでカメラを固定し、手ブレを防ぐ作業音が入らない静かな環境で収録する | 各工程をシーンごとに区切り、編集しやすくする字幕やテロップで補足し、視覚的理解を促す注意点やNG行動は、赤文字や図解で強調するBGMや効果音を使用して、視聴者の集中力を維持させる |
関連記事:動画マニュアルのメリットと作り方をわかりやすく解説
クリエイターの選定から依頼のやりとりを専任担当がサポート!
「自分でイラスト依頼のやりとりをするのが不安…」という方は、ぜひ「cone(コーン)」をご活用ください。
実際に、クリエイターの選定を行うのもなかなか大変… 「すぐに返信が来るかわからない…」「権利周りの相談で時間が掛かりそう…」など、商用利用では特にクリエイターへ依頼するまでに時間が掛かる事が多く、慣れていないと大変なんです…
そんな時は!
coneは法人企業からクリエイターへ依頼ができるサービス。
専任スタッフがクリエイターとのやりとりを代行し、納品までサポートします!
まずは、お気軽にご相談、お問い合わせください。
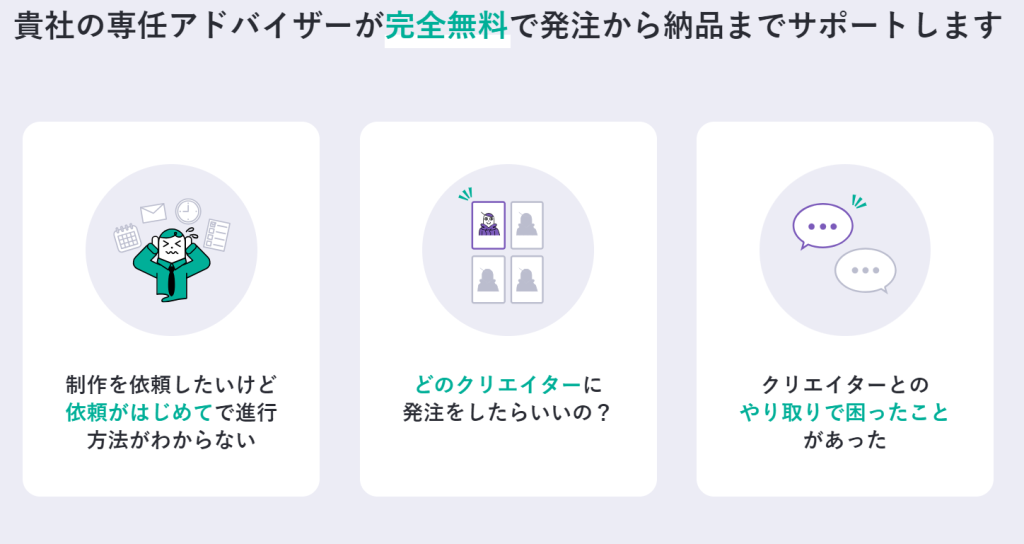
coneには、様々なニーズに対応できる実績豊富なプロのクリエイターが多数在籍しています。
ご希望の予算や納期に応じたご提案も可能です。
イラスト依頼のサポートや相談、「cone」の詳細をご希望の場合は、お気軽に「お問い合わせ」ください。